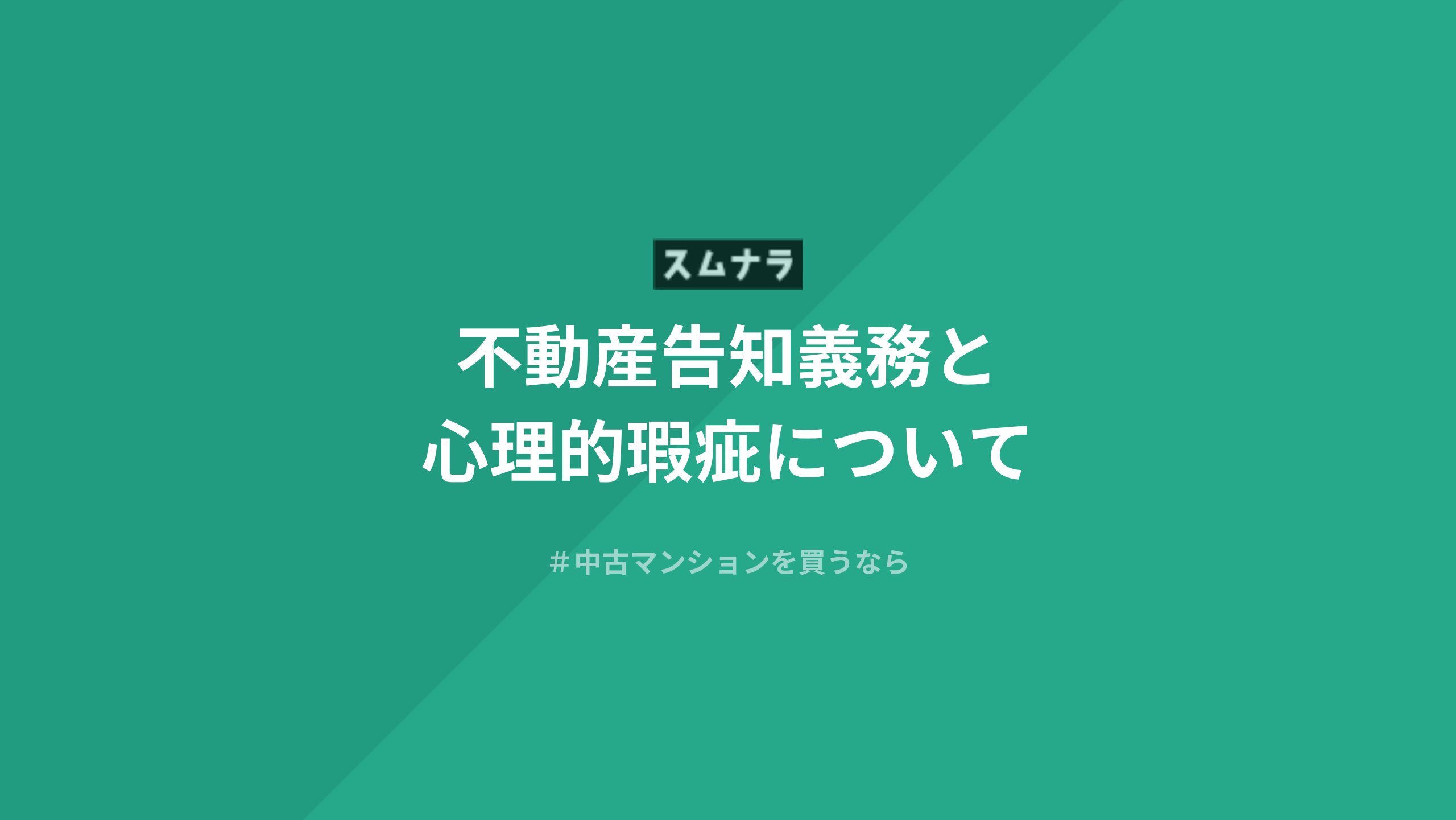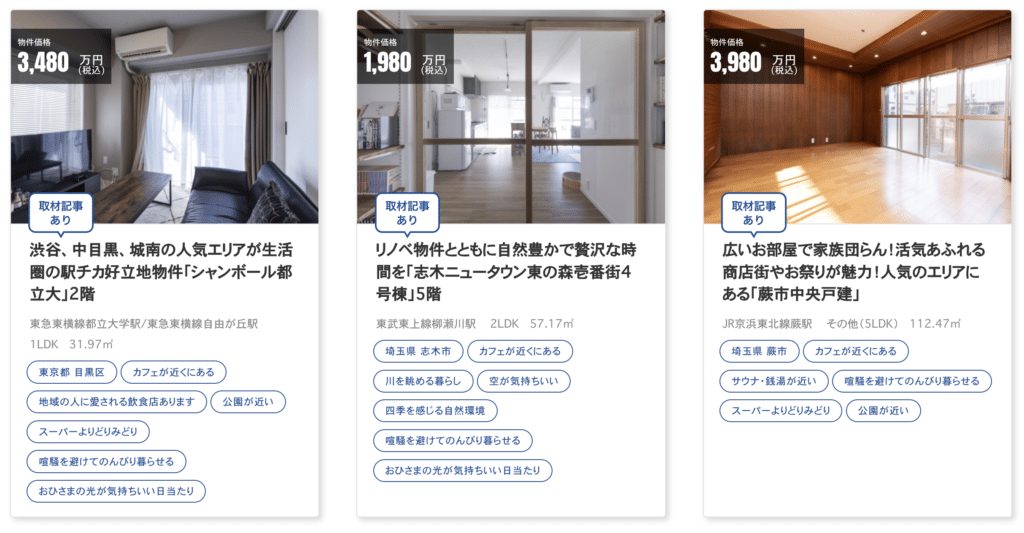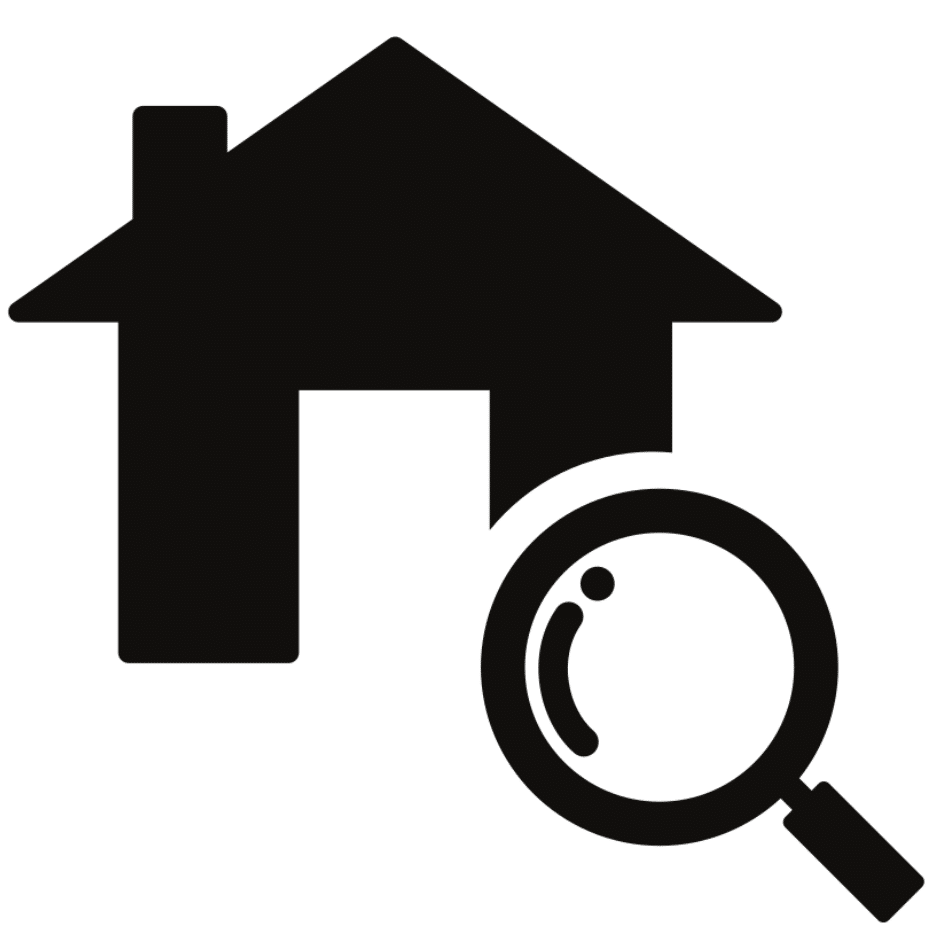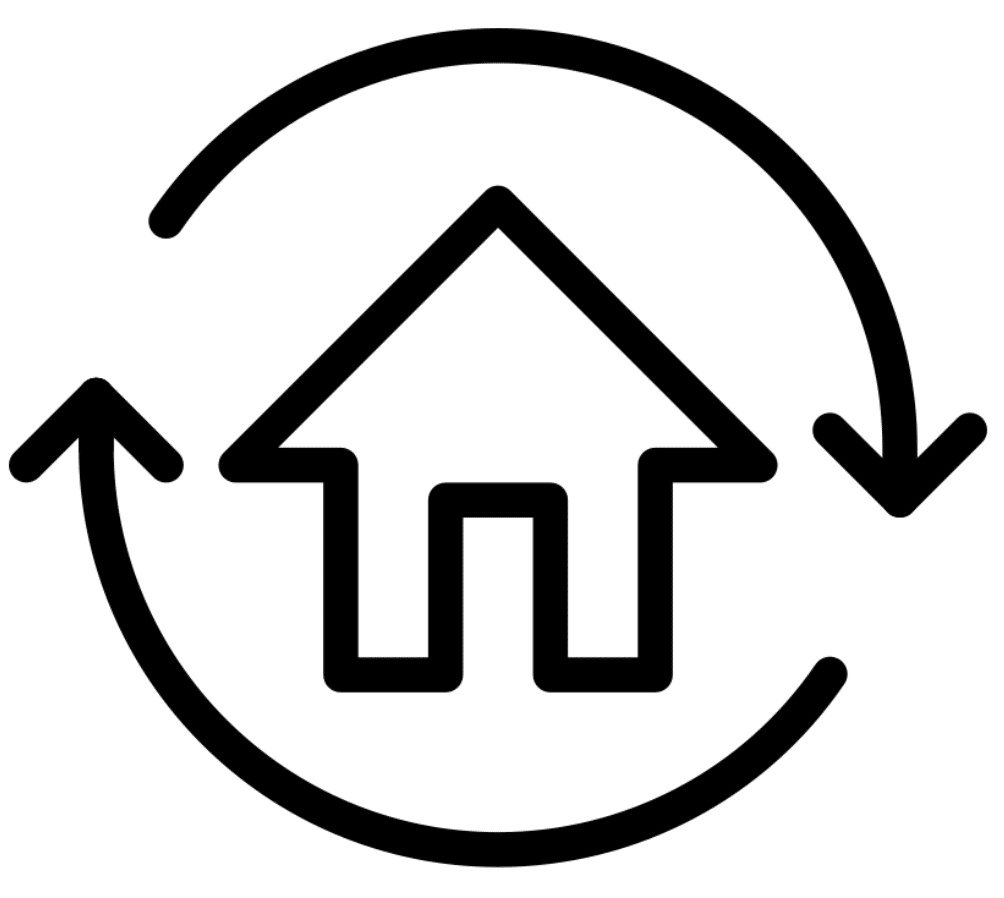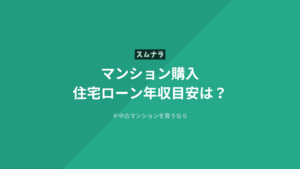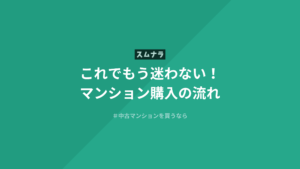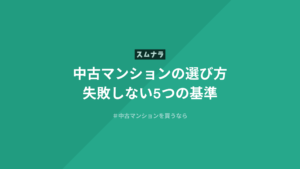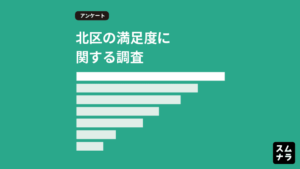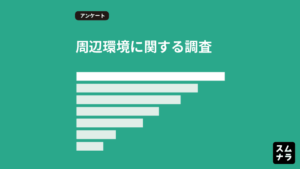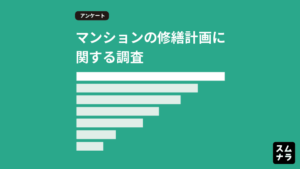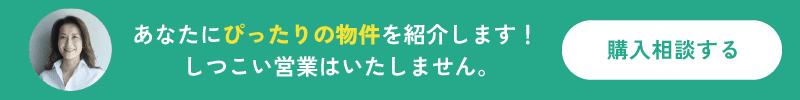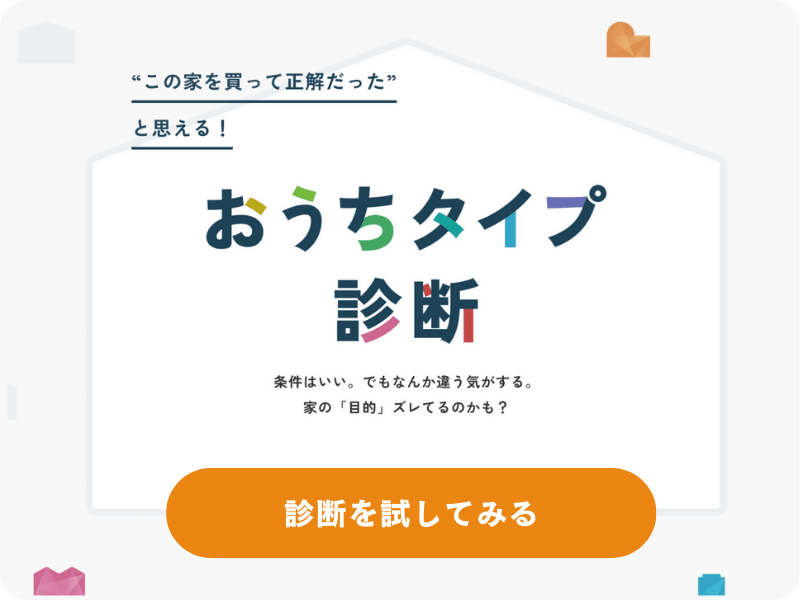「不動産の告知義務」と聞くと、事故物件や訳あり物件を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
告知義務の種類は物理的・法律的・環境的・心理的など複数ありますが、知らずに契約して後悔した、という声も少なくありません。
今回は、不動産の告知義務について、特に心理的瑕疵の範囲や告知義務の期間を中心にわかりやすく解説します。心理的瑕疵を避けて安心して取引する方法も紹介しますので、最後までご覧ください。

宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
元不動産営業のWEBライター。不動産会社で店長や営業部長として12年間勤務し、売買仲介・賃貸仲介・新築戸建販売・賃貸管理・売却査定等、あらゆる業務に精通。その後、不動産Webライターとして大手メディアや不動産会社のオウンドメディアで、住まいや不動産投資に関する記事を多く提供している。不動産業界経験者にしかわからないことを発信することで「実情がわかりにくい不動産業界をもっと身近に感じてもらいたい」をモットーに執筆活動を展開中。
本記事の内容は2025年6月6日時点の情報に基づいており、不動産市場の状況や関連法規、税制などは将来変更される可能性があります。最新の情報については、公式の情報源をご確認ください。
無料オンラインセミナー
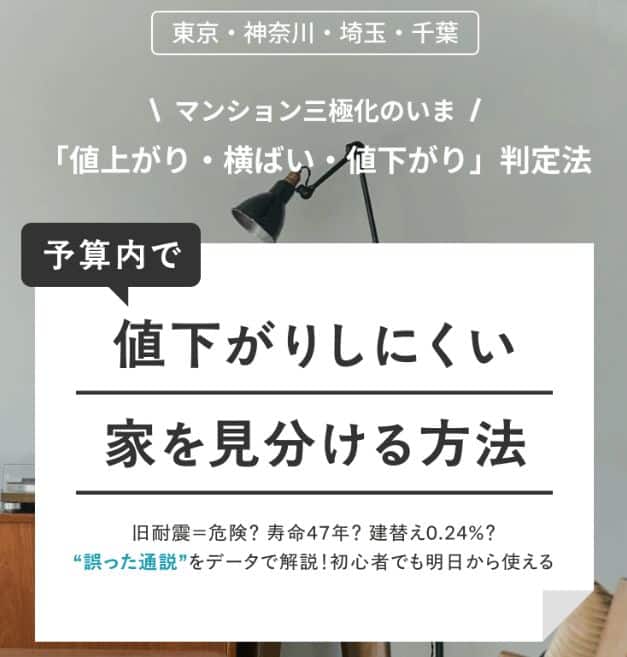
中古マンションを購入検討の方必見!
【セミナーの内容】
- 市場は「大吉・中吉・凶」の三極化
- 予算内で「中吉以上」を選ぶ方法
- 築年・立地・管理の3視点で探す
- 資産性・耐震性・寿命・建替えを解説
- 初心者歓迎・家族参加OK
- セールスなしで安心参加
不動産告知義務とは?告知事項は4種類

不動産の告知義務とは、物件に関する重要な欠陥や事実を売却前に買主へ伝える法的義務のことです。ここでいう物件の「問題」は「瑕疵(かし)」と呼ばれ、購入の際には注意が必要です。瑕疵には、以下の4つの種類があります。
- 物理的な瑕疵(雨漏り、シロアリなど)
- 法律的瑕疵(行政ルールの抵触など)
- 環境的瑕疵(騒音など)
- 心理的瑕疵(事故物件、近隣トラブルなど)
それぞれの瑕疵について詳しく解説します。
物理的な瑕疵(雨漏り、シロアリなど)
物理的な瑕疵とは、建物や土地そのものに生じた欠陥や損傷のことを指します。具体的には次のようなものが物理的な瑕疵に該当します。
- 雨漏り
- シロアリ被害
- 地盤沈下
- 壁のひび割れ
- 地中の廃棄物
こうした不具合が、物件購入後に発覚すると、住み出してからすぐに補修が必要になるケースも考えられます。物理的な瑕疵は、生活や建物の安全性に直接影響を及ぼす事項です。
 杉山
杉山そのため売主は取引前に物理的瑕疵について、必ず告知しなければならないと定められています。
法律的瑕疵(行政ルールの抵触など)
法律的瑕疵は、不動産が建築基準法や都市計画法、消防法などの法令に違反している状態を指します。購入前には気づきにくい場合もありますが、取引後に大きな制限や不利益が生じる可能性があるため、注意が必要です。代表的な法律的瑕疵は、以下のとおりです。
- 建物の建ぺい率・容積率がオーバーしている
- 接道義務を満たしていないため再建築ができない
- 防災設備が適切に設置されていない
- 建物の高さ制限に抵触し3階建てが建てられない
このような物件は、将来的に建て替えや増改築が制限されたり、住宅ローンの審査が通らなかったりなど不具合がおきることもあります。また、法律的瑕疵があると、買主が希望する用途で不動産が利用できない恐れもあるでしょう。



このため売主は事前に知っている法律的瑕疵について、必ず事前に告知するよう義務付けられています。
環境的瑕疵(騒音など)
環境的瑕疵とは、建物自体に問題がなくても、周辺環境が原因で生活に支障や不快感を及ぼす状態のことです。環境的瑕疵を具体的に挙げると、次のようなものがあります。
- 近隣の工場による騒音や振動がある
- ゴミ屋敷から悪臭がする
- 暴力団・宗教団体の施設が近隣にある
このように、周辺環境が劣悪で、物件の近くに住むことに心理的抵抗を感じるような施設がある場合、環境的瑕疵が適用されます。



環境的瑕疵があると生活の質に大きく影響し、後々のトラブルの原因にもなりやすいため、売主はこうした情報も買主に伝える義務があります。
心理的瑕疵(事故物件、近隣トラブルなど)
心理的瑕疵は、物件そのものに物理的な問題がなくても、過去の事件や事故、近隣トラブルなどで買主が心理的な抵抗や不安を感じる状態を指します。一般的に、心理的瑕疵がある物件は事故物件と呼ばれます。
心理的瑕疵の代表的な例は、次のとおりです。
- 物件内で自殺や他殺が起きた
- 孤独死が発生し、長期間発見されなかった
- 火災や事件が発生した
- 近くに反社会勢力の事務所がある
たとえ物件の機能面には問題がなくても、上記のような事柄があれば心理的瑕疵とみなされます。



心理的瑕疵は告知義務があるので事実は把握できますが、人によって感じ方が異なり、購入するかどうかについては買主の価値観に大きく影響されます。
心理的瑕疵の範囲|どこまで告知が必要?


心理的瑕疵の告知義務は、どこまでが対象となるのかという判断が難しいこともあります。そんな中、心理的瑕疵によるトラブルの頻発を背景に、令和3年10月に「人の死の告知に関するガイドライン」が国土交通省より策定されました。このガイドラインは、どのような場合に不動産会社が買主や借主へ人の死を告知すべきか、その基準や範囲を明確にしたものです。
ここからは、このガイドラインを踏まえ、心理的瑕疵の告知対象となる主なケースを紹介します。
自殺・他殺があった
自殺・他殺があった物件は「事故物件」とされ、買主や借主に必ず告知しなければなりません。なぜなら、自殺や他殺の事実は多くの人にとって心理的な抵抗感があり、購入・入居の判断に大きく影響を与えるからです。
特に室内で自殺・殺人事件が起きた場合、広告や重要事項説明書に「告知事項あり」と明記されることが一般的です。一方で自殺・他殺が室外で発生した場合や事件から相当期間が経過した場合、嫌悪感は少しずつ軽減すると考えられています。



このように、発生時期や場所によって心理的な影響には程度の差がありますが、国土交通省のガイドラインでは、特に自殺・他殺があった場合は明確に告知義務があるとされます。
人が亡くなり特殊清掃やリフォームを行った
人が亡くなり、遺体の発見が遅れて特殊清掃や大規模リフォームが必要になった場合も、心理的瑕疵として告知が必要です。自殺・他殺ではなく事件性のない孤独死や病死であっても、長期間放置された結果、異臭や汚染が発生し特殊清掃を実施したケースは告知の対象になります。



また、たとえリフォームなどの物理的な修復を行ったとしても「人が亡くなった」という事実は消えません。事故物件として扱われるので、必ず事前に伝える必要があるとされています。
嫌悪施設が近くにある
嫌悪施設が近くにある場合も心理的瑕疵として告知義務が発生します。嫌悪施設とは、住環境や心理面で抵抗感を抱く施設のことです。主な嫌悪施設として、以下が挙げられます。
- 火葬場
- 墓地
- 暴力団事務所
- 刑務所
- 風俗店
- ゴミ処理場
どの施設が嫌悪施設として該当するかは地域性や個人の感覚によって異なります。



しかし、買主が知っていれば購入を見送る可能性が高いと考えられる要素については、重要事項説明書に明記して伝える必要があります。
近くに迷惑行為を行う人がいる
近くに迷惑行為を繰り返す住民がいる場合も、心理的瑕疵として告知が必要となります。例えば、神経質なクレームを繰り返したり騒音トラブルを抱えていたりする住人などが、隣近所に居住するなどのケースです。
このようなトラブルは購入後の生活に大きなストレスを与える場合が多く、買主や借主の判断に大きく影響するでしょう。



迷惑行為を繰り返す住民の存在を知っていながら告知しなければ、後々損害賠償や契約解除などのリスクにも繋がることもあるため、告知が必要です。
無料オンラインセミナー
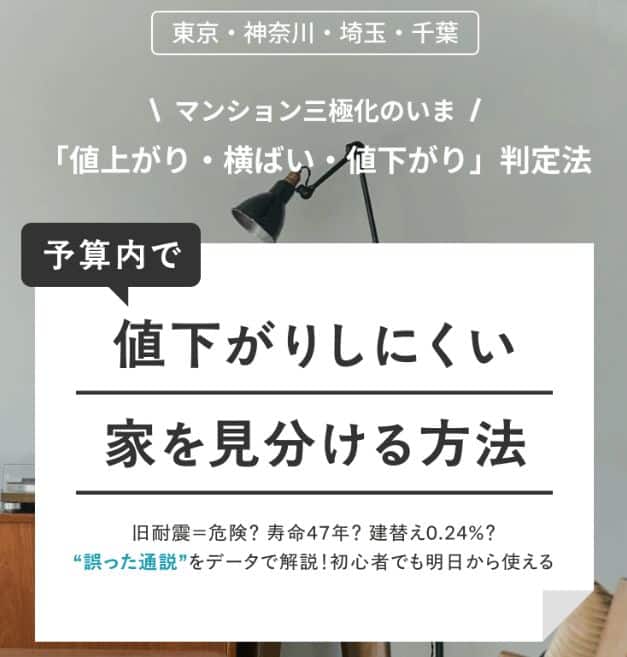
中古マンションを購入検討の方必見!
【セミナーの内容】
- 市場は「大吉・中吉・凶」の三極化
- 予算内で「中吉以上」を選ぶ方法
- 築年・立地・管理の3視点で探す
- 資産性・耐震性・寿命・建替えを解説
- 初心者歓迎・家族参加OK
- セールスなしで安心参加
心理的瑕疵の確認方法


建物に傷があるなどの物理的瑕疵は専門家に調査を依頼すれば、ある程度は避けられます。しかし、心理的瑕疵は目に見えないので、あらゆる角度から情報を集めることが大切です。ここでは、心理的瑕疵を調べる際に主に使われている4つの方法について解説します。
不動産会社へ問い合わせる
心理的瑕疵を調べるには、まずは不動産会社へ問い合わせましょう。自殺・他殺や隣人トラブルなど事故物件に該当する場合には、法律によって不動産会社は買主に対して告知する義務があります。
ただし、心理的瑕疵の範囲は曖昧で、不動産会社ごとに認識が異なるのも実情です。また、不動産会社がすべての情報を把握しているとは限りません。そのため、心理的瑕疵が心配であれば、不動産会社に問い合わせるだけでなく自分自身で調べるのがおすすめです。



中には、不動産会社よりも売主や近隣の住人に確認する方が正確な情報を得られるケースもあります。
物件資料に「告知事項あり」の記載がないかを確認する
物件資料に「告知事項あり」や「心理的瑕疵あり」などの記載があるかどうかも、心理的瑕疵を確認する手がかりになります。物件に心理的瑕疵がある場合、備考欄にその旨を記載していることが多いです。
購入を検討している物件資料を見る際は、物件概要や備考欄を細かくチェックしましょう。
ただし「告知事項あり」と記載があっても、必ずしも心理的瑕疵があるとは限りません。



物理的瑕疵や環境的瑕疵が理由となっていることもあるため、気になる記載を見つけたら、不動産会社にその内容について詳しく聞いておくと安心です。
売主や近隣住民に直接聞きこむ
心理的瑕疵を確認するには、売主や近隣住民に直接話を聞く方法もあります。なかには、不動産会社も把握していない事実が住民の間で噂として広まっており、入居後に近隣から事故物件だと知らされるケースもあります。
心理的瑕疵が気になるのであれば、内見時に「この地域で事件や事故がありましたか?」などと、売主に率直に聞いてみるのも1つの方法です。



購入する意思があるとわかれば、売主は丁寧に教えてくれる可能性が高いでしょう。
事故物件情報が掲載されたサイトで調べる
事故物件情報サイトを活用するのも、心理的瑕疵を調べる方法の1つです。「大島てる」などのサイトでは、全国の事故物件情報が地図上で閲覧でき、住所を入力するだけでその物件が事故物件に該当するかが確認できます。
ただし、これらのサイトに載っている事故物件情報は一般ユーザーの投稿によるものが多く、必ずしも正確とは限りません。



ネット上の情報はあくまで参考として扱い、最終的には不動産会社や近隣の住人に確認することをおすすめします。
事故物件の告知義務の期間|時効はある?


事故物件の告知義務期間は、売却と賃貸でルールが異なります。ここでは、それぞれのケースについて解説します。
売却の場合は時効はない
売却の場合、事故物件の告知義務には時効がありません。売主が過去の自殺や他殺などの心理的瑕疵を知っている場合、たとえ事件から何十年経っていても買主に伝える必要があります。これは、不動産売買が高額な取引であり、買主の生活や物件の資産価値に大きな影響を与えるためです。
例えば、30年前の殺人事件でも、買主にとっては重要な判断材料です。売主が事実を隠して売却した場合、後から発覚すると損害賠償や契約解除といったトラブルに発展しかねません。



そのため、不動産売買では期限を問わず、正確な情報を伝えなければならないとされています。
賃貸の場合は原則3年
賃貸の場合、告知事項が発生してから原則3年間が告知義務の目安です。これは「人の死の告知に関するガイドライン」で「概ね3年」と明記されており、この期間は新たな入居者に事故の事実を説明する必要があります。
ただし、これには例外があります。事件性が高く社会的に注目された場合や、近隣住民の記憶に強く残っている事件の場合は、3年を超えても告知が必要です。また、入居希望者から過去の事故について問い合わせを受けた場合は、3年を過ぎても説明しなければなりません。



ガイドラインが策定される以前は「一度でも入居者がいれば告知は不要」と考える不動産会社も少なくありませんでした。しかし、現在ではこの考え方は見直され、最低でも3年間は告知が必要とされています。
告知義務を行う時期とタイミング
物件について告知すべき内容は、契約締結前に伝えておく必要があります。具体的には、物件の広告や内見時、買主から質問があった際など、商談が開始された時期から情報を開示するのが基本です。
また、契約成立後に新たな事実が判明した場合も、速やかに相手方へ伝えなければなりません。



例えば、引渡し前に新たな告知事項が発覚した場合には、すぐに買主に説明し、必要に応じて契約内容の見直しも検討します。
まとめ
不動産の告知義務には、物理的・法律的・環境的・心理的瑕疵の4種類があり、なかでも心理的瑕疵は事故物件や近隣トラブルなど、買主の心理に大きな影響を与える項目です。心理的瑕疵は不動産会社へ問い合わせるだけでなく、近隣住民への聞き込みや物件資料の細かい確認など、多角的に情報を収集することが重要になります。