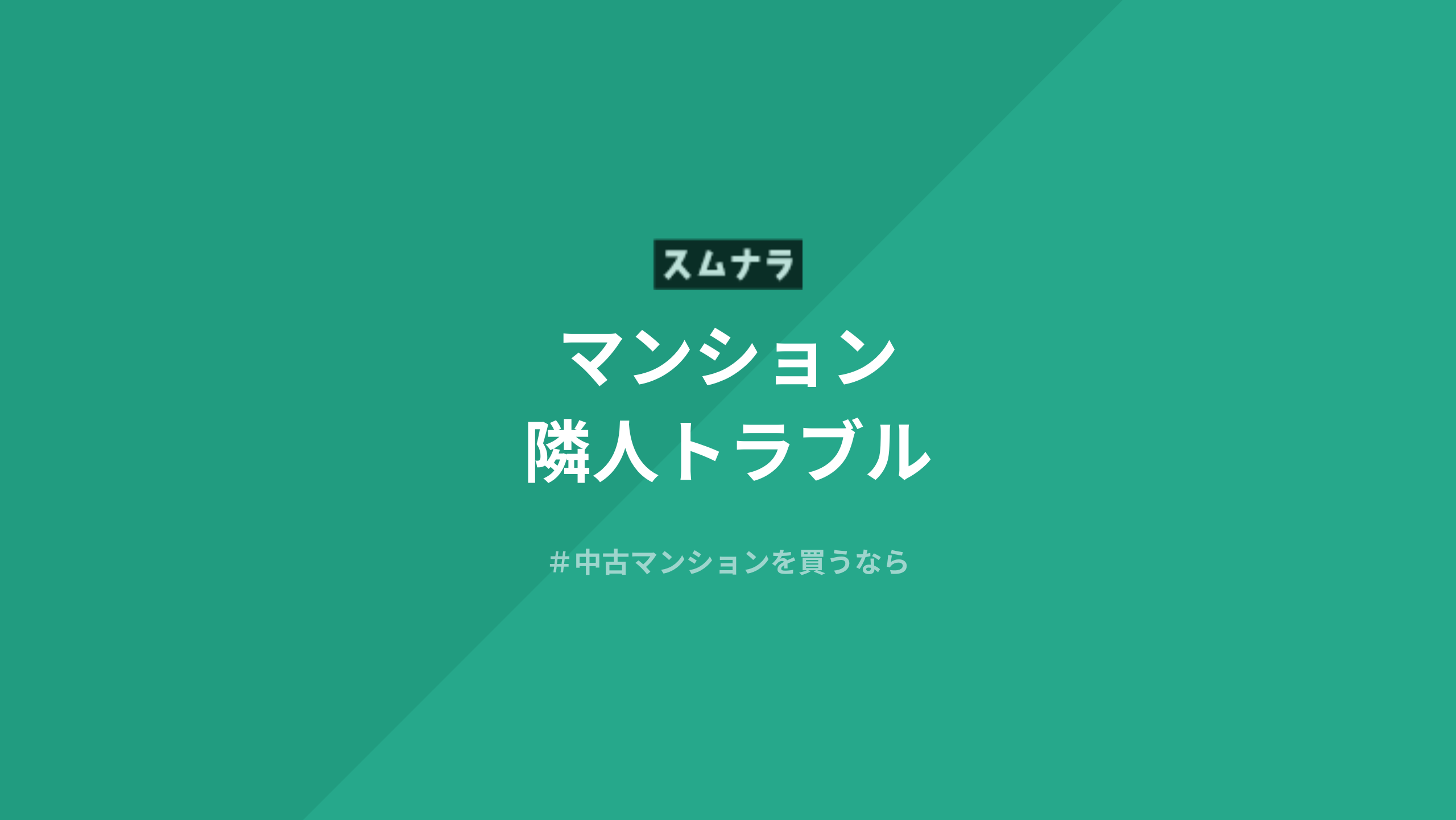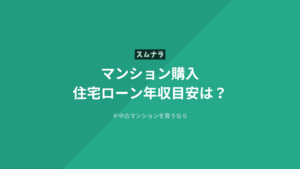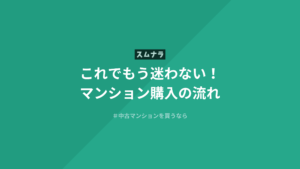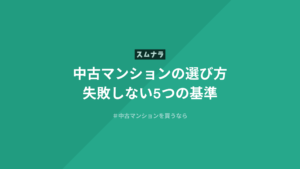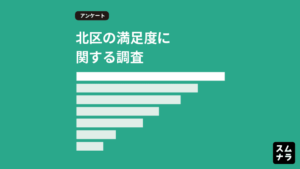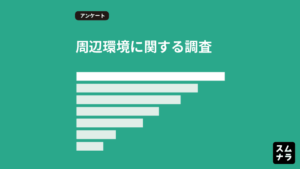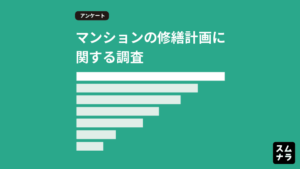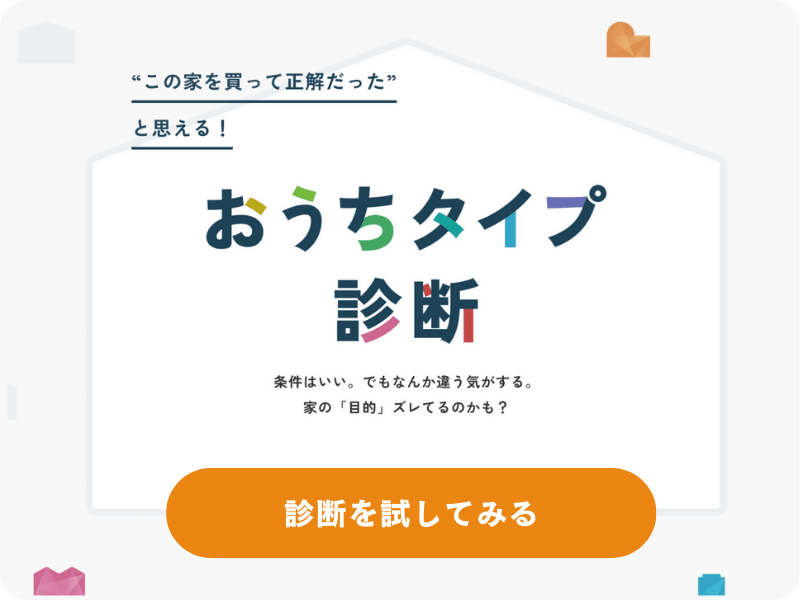マンション選びで見落としがちなのが、「隣人トラブル」のリスクです。どんなに間取りや設備が気に入っても、隣人のマナーでマンションの住み心地は大きく左右されてしまいます。
実際に、国土交通省が5年おきに実施するマンション総合調査の結果によると、令和5年度の調査で、トラブルがないと答えたマンションは、わずか16.0%です。トラブル発生の原因の60.5%が「居住者間のマナー」という結果が出ています。
この記事では、マンションの隣人トラブルの実態と万が一の対処法、さらに購入前のチェックポイントまで、わかりやすく紹介します。安心で快適なマンション選びの参考にしてください。

行政書士/司法書士/宅地建物取引主任士
大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。
本記事の内容は2025年7月23日時点の情報に基づいており、不動産市場の状況や関連法規、税制などは将来変更される可能性があります。最新の情報については、公式の情報源をご確認ください。
中古マンション販売サイト「スムナラ」なら、
感覚ではなく数字と根拠で、後悔しない住まい選びができます。
 世田谷区
世田谷区
空間がゆるやかに繋がる専用庭付きリノベーション住宅「祖師ヶ谷大蔵センチュリーマンション」1階
5,180万円
 世田谷区
世田谷区
都会的な利便性と豊かな自然が調和するリノベ済み物件「尾山台リバーサイドハイデンス」1階
4,580万円
 千葉市
千葉市
都内へ好アクセスな都市と自然が共存する暮らし「エヴァーグリーン千葉中央」4階
2,680万円
 茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
約90㎡のゆとりと明るいリビングが魅力の3LDK「コスモ茅ヶ崎プレシオ」9階
1,980万円
 横浜市
横浜市
緑豊かな住環境と広々とした3LDK「三保ガーデン」
3,580万円
 北区
北区
築浅で最新の設備が満載!駅チカ2LDK物件「プレシスヴィアラ田端」9階
7,870万円
よくある隣人トラブルの事例

マンション生活では、隣人とのトラブルは、多くの住民が経験する問題の1つです。実際に多々発生しているトラブルの種類は、次のようになります。
- 騒音トラブル
- 駐輪場・駐車場トラブル
- ペット関連トラブル
- ゴミ出しトラブル
- 共用部分の使用マナーを巡るトラブル
ここからは、それぞれの具体的な内容や注意点を詳しく解説します。
騒音トラブル
マンションのトラブルでもっとも多いのが騒音問題です。令和5年の調査によると、居住者間のマナーに関するトラブルのうち43.6%が騒音の問題でした。
上階から聞こえる子どもの走り回る音や大人の足音は、特に夜間や早朝に問題となりやすいものです。睡眠を妨げる深刻な悩みにも、繋がるかもしれません。
また、テレビや音楽、扉の開閉音といった日常的な生活音も、建物の構造によっては大きく響いて、トラブルの原因となることがあります。
 遠藤
遠藤楽器の演奏も、演奏者にとっては美しい音色でも隣人には迷惑となるケースが少なくありません。
駐輪場・駐車場トラブル
マンションでは、駐車場や駐輪場でのトラブルも発生しやすく、居住者間のマナーを巡るトラブルのうち18.2%を占めます。無断駐車や指定区画外への駐車・駐輪は、契約者が利用できなくなり深刻です。
特に「停めた車両を動かしてくれない」という状況は、大きな問題になります。長期間放置された車両や自転車は、邪魔になるだけでなく見た目も悪く、住環境を悪くします。



通路を塞ぐ駐車や、私物を駐車場に置く行為も、日常的なストレスやトラブルの原因となり、利用者間トラブルの引き金になります。
ペット関連トラブル
ペットの飼育をめぐるトラブルも、居住者マナートラブルの14.2%と高い割合で発生しています。ペット禁止物件での無断飼育はもちろん、ペット可物件でも問題が起きないとは限りません。
犬の鳴き声や猫の夜鳴き、共用部分でのマナー違反が代表的なトラブルです。



他にも、ペットの毛や臭いが原因でアレルギーや衛生面での問題がおきたり、ベランダでペットのブラッシングによって毛が飛散したりなども、隣人間のトラブルの原因となります。
ゴミ出しトラブル
ゴミ出しに関するトラブルも頻繁に発生する問題の1つです。ゴミの種類ごとに出せる日が決められている物件では、決められた時間や曜日が守られなかったり、分別ルールを無視して混合ごみを出したりする住民が現れることがあります。
分別ルールを無視したゴミ出しや不適切なゴミの廃棄は、マンションの美観や衛生に問題を起こすだけでなく、臭いや害虫の発生、さらには害獣の侵入を招くことがあります。



ひとりのルール違反が、他の住民を巻き込み、マンション全体の問題へと発展するケースも少なくありません。
共用部分の使用マナーを巡るトラブル
共用部分の使用マナーをめぐるトラブルも多く報告されています。廊下や玄関前への私物放置は、見た目だけでなく避難経路を塞ぐ安全上の問題にもなりかねません。
エレベーター内での大声での会話や長時間の占有、バルコニーでの喫煙による煙や臭いの問題も隣人関係を悪化させる要因になります。



さらに、洗濯物の干し方についても、規約を守らないと、景観を損ねたり隣戸に迷惑をかけたりする可能性があります。
マンションの隣人トラブルが起きた時の対処法


隣人トラブルが発生した際は、感情的になって直接相手に苦情を伝えるのは禁物です。当事者同士の話し合いで解決しようとすると、問題がこじれるだけでなくむしろ関係が悪化してしまうことも多いので注意が必要です。
まずは冷静に状況を整理し、第三者を交えた解決策を検討しましょう。
初期対策
マンションで隣人トラブルが起きた時は、最初に管理会社や管理組合に相談しましょう。管理会社のサービスには「住民間のトラブル調整」もあり、匿名での注意喚起や掲示、文書による周知など、住民間の関係を悪化させないような対応をしてくれます。
相談をする際には、客観的な証拠があった方がスムーズです。トラブルを見聞きした時は、なるべくその場で以下のように記録を残しましょう。
- 騒音であればスマートフォンやレコーダーを使って録音する。
- ゴミ捨て場や共用部分の問題であれば撮影する
記録には、発生した日と時間・状況、被害があればその内容を書いたメモを添えると、説明がしやすくなります。


初期対策で解決しない場合:弁護士や警察など
管理会社や管理組合の対応でも隣人トラブルが収まらない時は、外部の専門家への相談も検討しましょう。まず、相談先として考えられるのは弁護士ですが、状況によっては警察へ相談する必要があるケースもあり得ます(警察対応についてはこの後の項目で詳しく説明します)
弁護士に依頼できる範囲は、住民同士やマンションの管理組織との交渉だけでなく、被害が大きい時は損害賠償請求も含まれます。



証拠収集から法的手続きまで幅広くサポートしてくれますが、費用が発生するため、十分な証拠がそろった段階で相談することが効果的です。
警察に通報していいのか迷ったときの判断の仕方
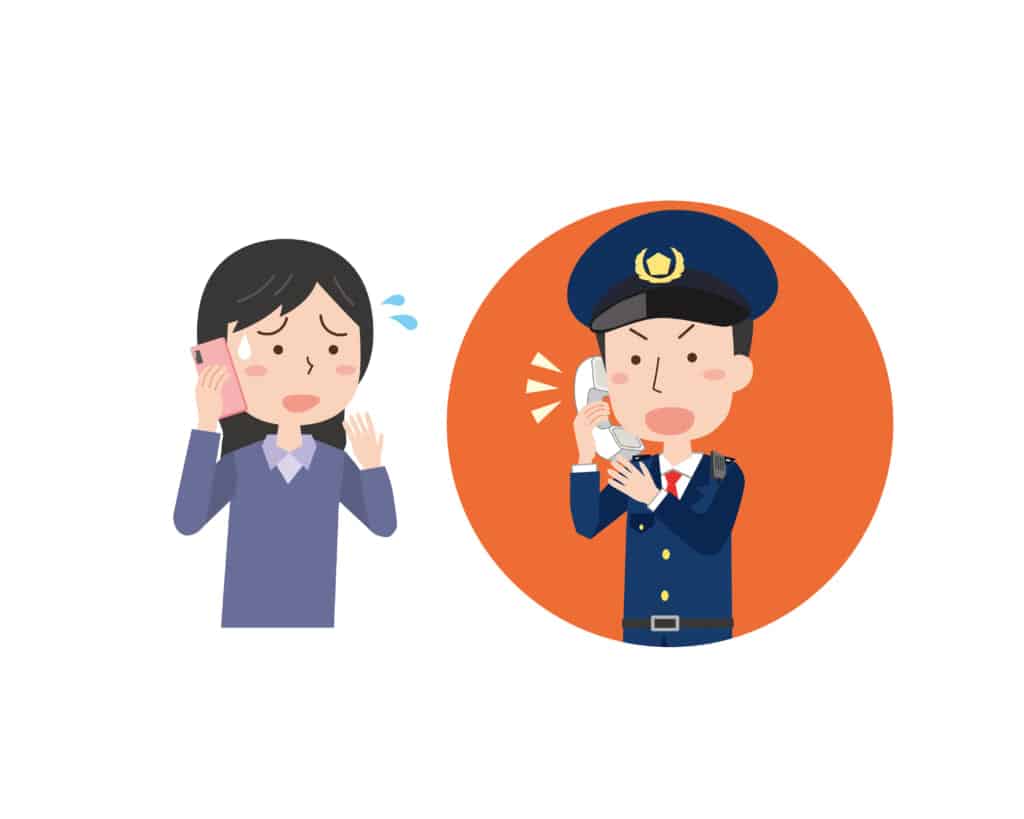
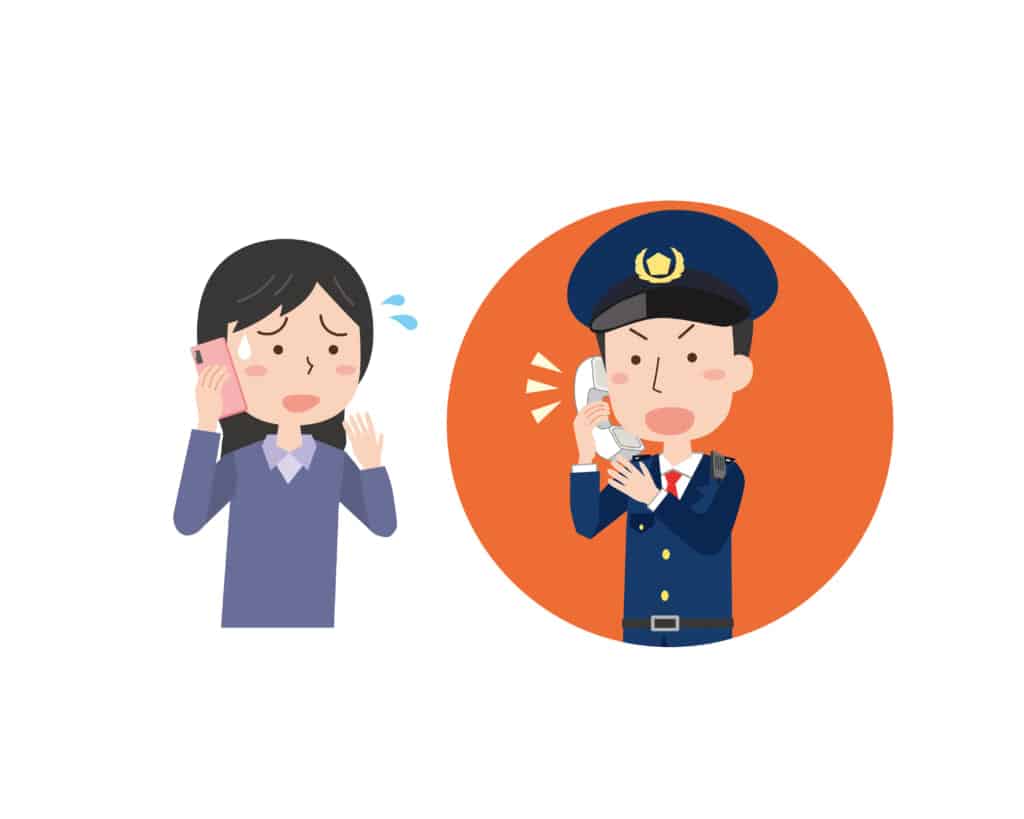
隣人トラブルで警察に相談するのは「大ごとにしたくない」と、ためらう方も多いでしょう。しかし、度を越えた騒音や身の危険を感じる状況では、迷わず警察に相談する選択肢も考えましょう。
とはいっても、警察に通報していいのか判断がつかない、警察がどこまで対応してくれるか不安に思うこともあるかもしれません。そんな場合には、警察相談専用電話(#9110)に相談するのも1つの方法です。
警察対応になるレベルの被害がある
隣人トラブルが軽犯罪法違反に該当する場合、警察の対応対象となります。具体的には、警察から注意を受けても、異常を感じる程に大きな音を出し続けて近隣に迷惑をかけるケースなどがあります。目安として例をあげるなら、地響きのような音が長時間続いて一睡もできない状況や、ストレスで体調不良になるレベルが該当します。
また、脅迫や暴行、器物破損、不法侵入などの行為は明確な刑事事件となり、警察が対応します。



生活を脅かす継続的な嫌がらせについても、証拠がそろえば警察に相談すべきケースといえるでしょう。
身の危険を感じる・緊急性が高い
身の危険を感じる状況では、迷わず110番通報をしてください。隣人が部屋のドアを叩いていて今にも乗り込んできそうな状況や、暴力を受けそうになっている場合は緊急事態です。
騒音によるストレスで通院が必要になる程健康被害がある場合も、警察へ相談すべきでしょう。
ときには、自分自身が被害を受けていなくても、周囲の住民が追い込まれてしまうことがあります。



トラブルがエスカレートして、他の住民や子ども、高齢者など弱い立場の人へ被害が及びそうな場合も、警察への通報をためらわないでください。
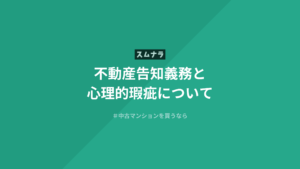
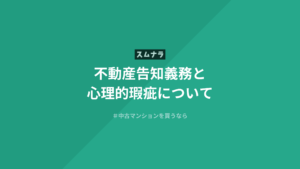
隣人トラブルを回避するポイント
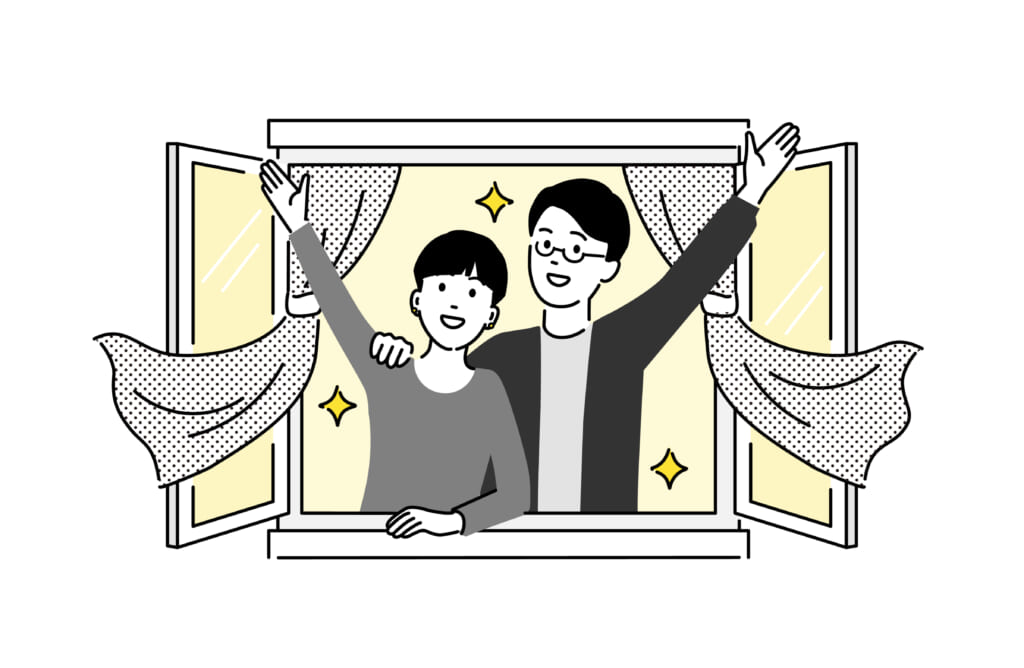
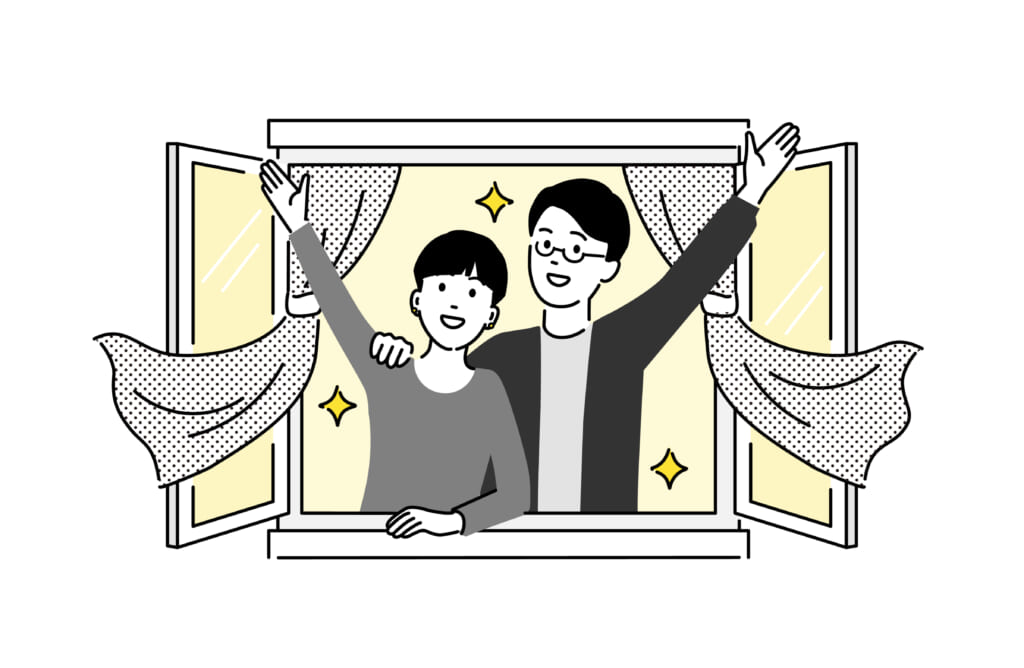
隣人トラブルを未然に防ぐには、物件選びの段階から、しっかりと検討することが大切です。
特に中古マンションの場合には、隣人関係や住環境が事前にわかりにくいので、慎重な確認が欠かせません。隣人調査や物件の構造・管理状況をしっかり確認しておくかどうかは、将来の住み心地を左右します。
また、入居後に近隣と良い関係を築いていくことも、長く快適に暮らすためには大切なポイントです。
隣人調査
中古マンション購入前の隣人調査は、将来のトラブルを回避するために欠かせません。内見時には建物周辺の環境だけでなく、共用部分の使用状況や掲示板の内容も、あわせてチェックしましょう。
また、管理会社へ住民層を確認するのもおすすめです。ファミリー世帯と単身世帯の比率、文化が異なる国の住民の割合などを把握しておけば、生活スタイルの違いによるトラブルリスクがみえてくるでしょう。
さらに、時間帯を変えて現地確認をするのも重要です。購入を検討しているマンションには、平日の昼間だけでなく夜間や休日にも足を運び、騒音レベルや住民の生活パターンを観察しましょう。
例えば、子どもの遊び声や車の出入り頻度、洗濯物の干し方などは、将来の生活環境を知るポイントになります。
物件選びでの注意点
一般にマンションの築年数は、防音性能の目安の1つです。比較的新しいマンションは厳しい遮音規定に従って建設されています。特に1997年以前の古いマンションは、建築当時には防音の規定が、あまり普及していませんでした。ですから、なかには音が漏れやすい構造のマンションもあります。防音効果もある「二重床構造」も、標準化されたのは2000年以降です。


マンションがファミリー向けか単身向けかによっても、違いがあります。ファミリー向け物件は各戸の入居期間が長いため、住民同士も顔見知りになりやすく、落ち着いた環境が保たれやすいといったメリットはありますが、子どもの足音など生活音による騒音問題が発生しやすい傾向があります。逆に単身向け物件は、入居期間が短く入れ替わりが激しいため住民同士の関係が薄くなりがちですが、生活音のトラブルは比較的少なめです。



このように、物件選びには多くの注意点があり、どこに重きを置くかは入居者のライフスタイルや価値観にも左右されます。
管理規約や管理費用の積立状況をチェックする
管理規約・使用細則は、入居後のトラブルを避けるためにも確認しておきましょう。これらには、ペット飼育の可否、楽器演奏のルール、共用部分の使い方などが詳細に定められています。事前に内容を把握しておけば、思わぬトラブルを回避できます。
また、修繕積立金・管理費の状況も、将来に直結する大切な確認事項です。修繕積立金の全国平均は月額13,054円ですが、この統計の中には計画的な積立ができておらず積立金が不足しているマンションも含まれています。
実際に、マンションの36.6%は、十分な積立ができていないという国土交通省の報告もあります。積立不足のままでは、将来的に大規模な修繕が行えず、建物の老朽化やトラブルの恐れもあります。
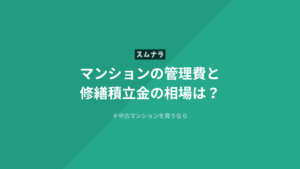
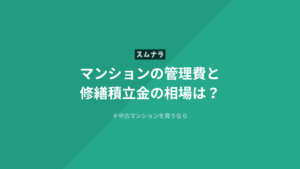




なお、空室率の高いマンションの場合、管理組合運営に問題を抱えている可能性もあります。
これらのチェックには専門的な知識を必要とする場合もあり、個人で詳細を見極めるのは難しいこともあります。管理規約の内容や積立金の状況、長期修繕計画の中身まで、しっかり確認するには時間と経験も必要です。
まとめ


マンションの隣人トラブルは、騒音や駐車場問題、ペット関連など多岐にわたり、国土交通省の調査では6割以上のマンションで何らかのトラブルが発生していると報告されています。こうしたトラブルが発生したら、感情的にならず、まずは管理会社に相談しましょう。その後、必要に応じて専門家への相談も検討することが大切です。
トラブルを避けるためには、購入前の調査が欠かせません。築年数や建物の工法、時間帯を変えた現地調査、管理規約や積立金の状況など、チェックすべきポイントは多岐にわたります。これらの調査には専門的な知識と経験が必要です。しかし、詳細な調査ノウハウを持つ仲介会社は限られています。だからこそ、会社選びがマンション購入成功のポイントとなるのです。
スムナラは、リノベーション会社として多くの中古マンションの売買に携わってきました。その豊富な経験を活かし、建物構造から管理状況、近隣環境まで多角的な視点でマンションを評価しています。隣人調査から管理組合の運営状況確認、一般的な仲介会社では対応が難しい項目まで、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。隣人トラブルのリスクをできるだけ減らし、安心して暮らせる住まいを選びたいとお考えの方は、ぜひお気軽にスムナラへご相談ください。