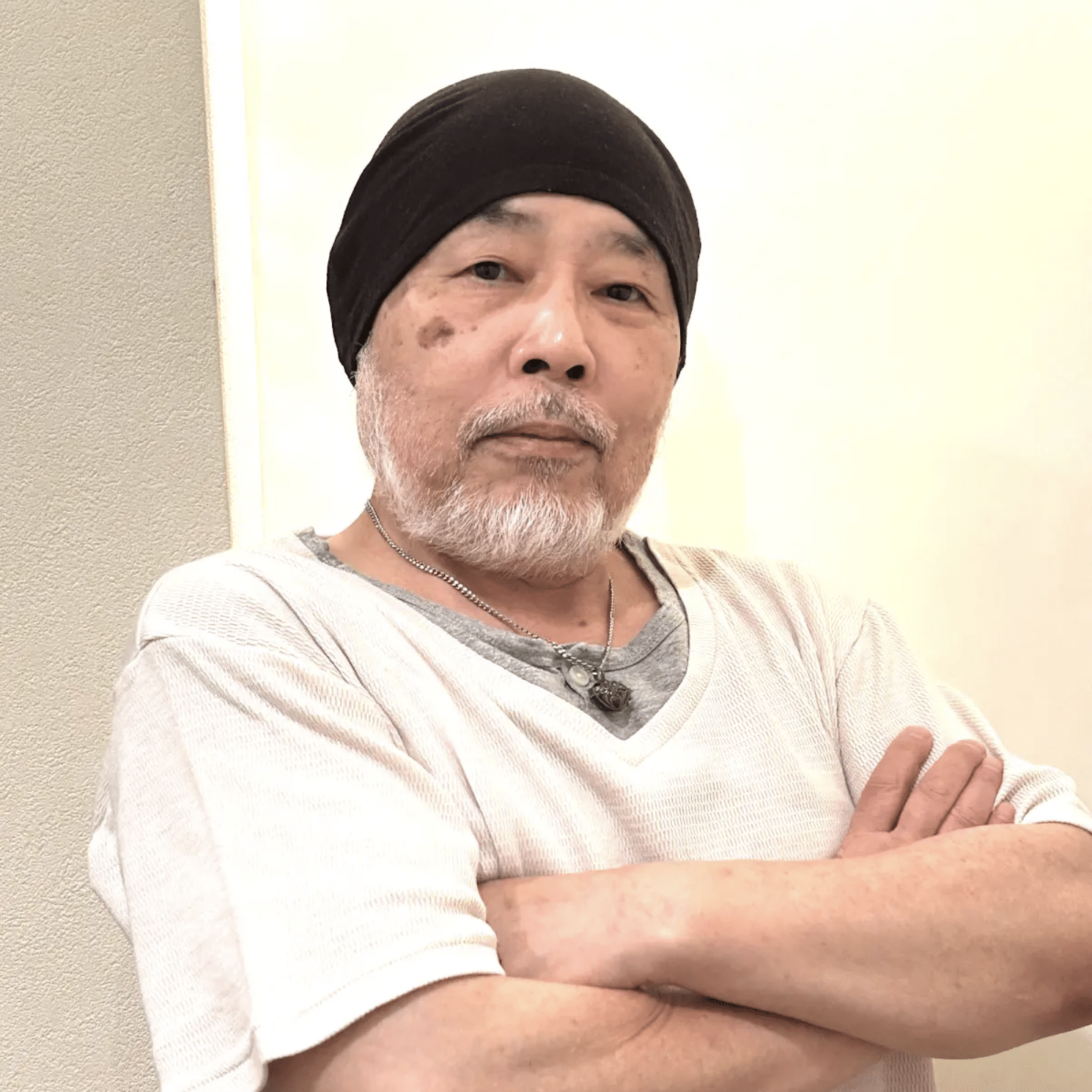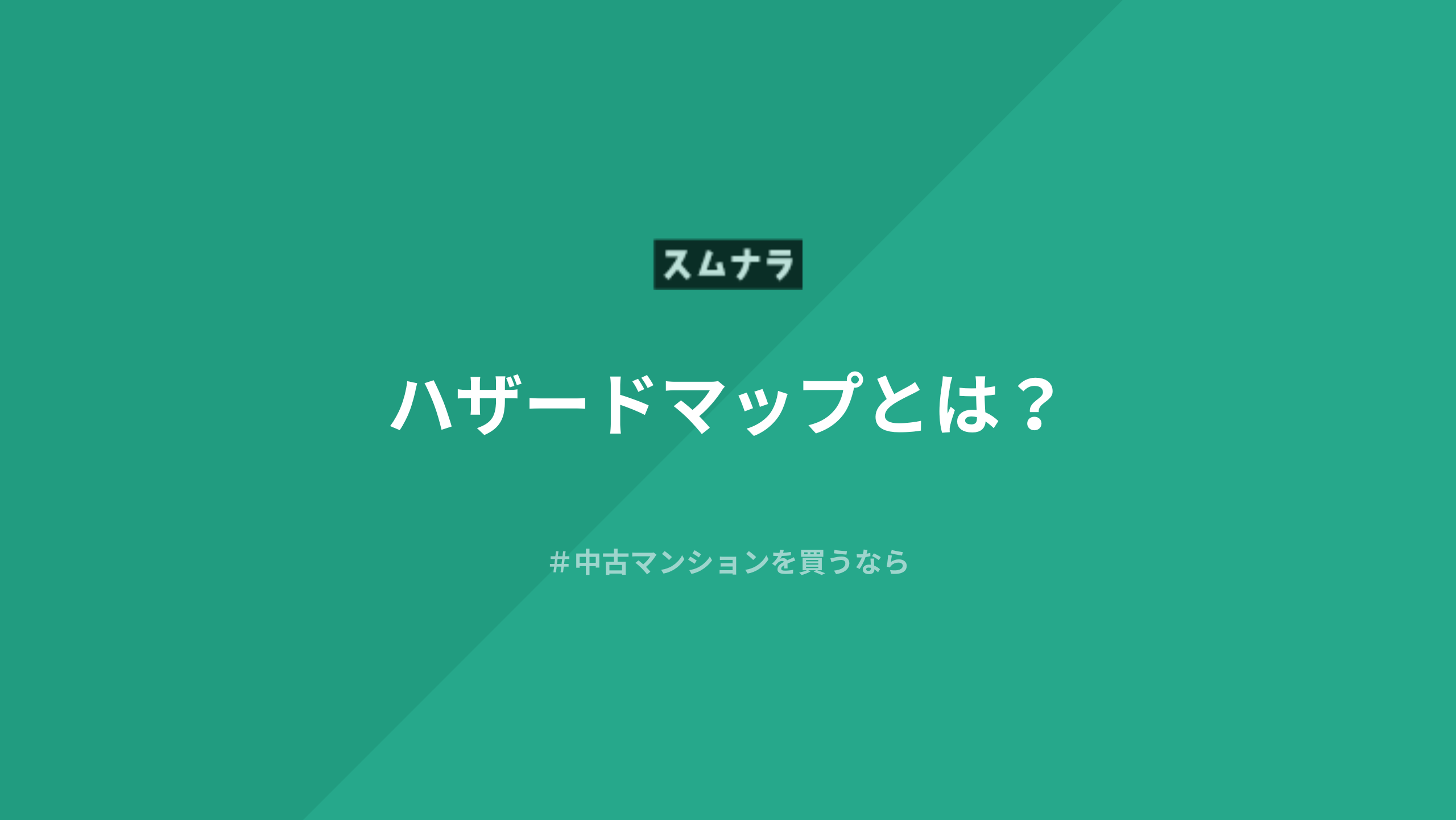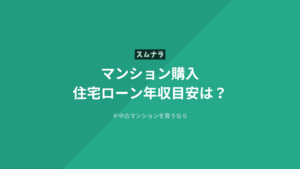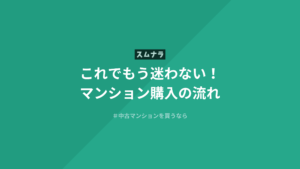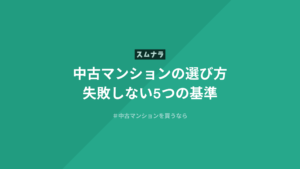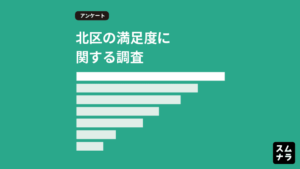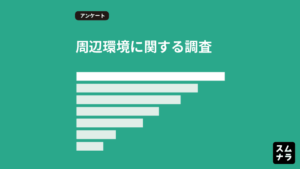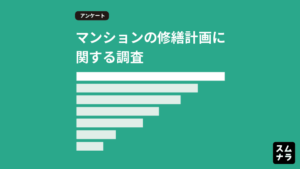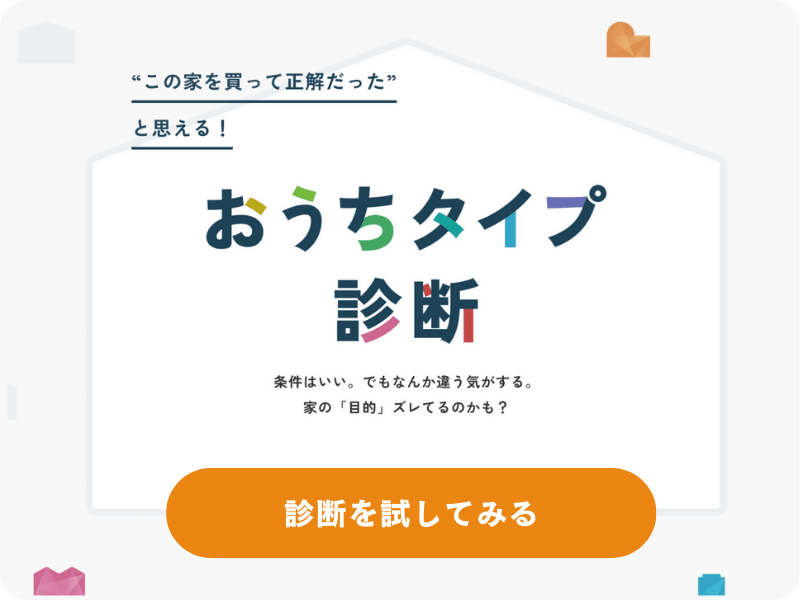「ハザードマップは台風や地震が起きた時に見るもの」と考える方も少なくありません。
ところが実際には、マンションを購入する際にも各種ハザードマップの確認は欠かせません。事前にエリアごとの災害リスクを理解しておくことで、自分や家族が安心して暮らせる物件選びに繋るからです。
スムナラでは入居時にハザードマップを活用し、マンションの安全性や災害時の避難所についてもしっかりご案内しています。
今回は、防災士の視点から「防災マップとの違い」「利用する場面」「見方と使い方」「確認しておきたいポイント」の4つを解説します。これらを理解しておくことで、安全なマンション購入の大きな目安となるでしょう。
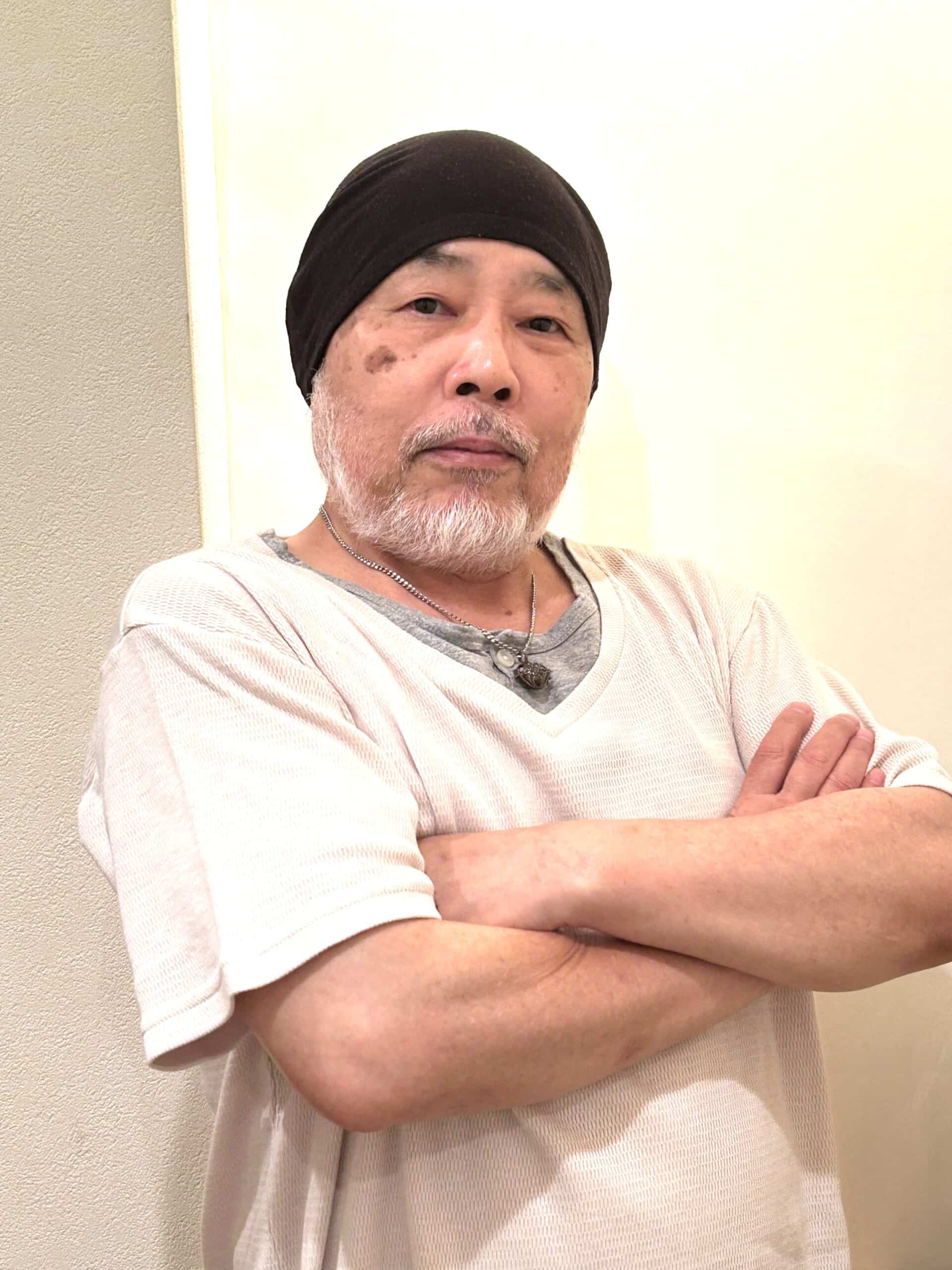
防災士/ひょうご防災リーダー/ひょうご防災特別推進員/ひめじ防災マイスター
長年、自治体のハザードマップ作成業務に携わり、洪水・土砂災害・地震・津波・高潮など、あらゆるハザードマップを作成。2014年よりWebライターとしても活動をはじめ、多数のメディアで防災にまつわる情報を発信している。
本記事の内容は2025年8月28日時点の情報に基づいており、不動産市場の状況や関連法規、税制などは将来変更される可能性があります。最新の情報については、公式の情報源をご確認ください。
中古マンション販売サイト「スムナラ」なら、
感覚ではなく数字と根拠で、後悔しない住まい選びができます。
 世田谷区
世田谷区
空間がゆるやかに繋がる専用庭付きリノベーション住宅「祖師ヶ谷大蔵センチュリーマンション」1階
5,180万円
 世田谷区
世田谷区
都会的な利便性と豊かな自然が調和するリノベ済み物件「尾山台リバーサイドハイデンス」1階
4,580万円
 千葉市
千葉市
都内へ好アクセスな都市と自然が共存する暮らし「エヴァーグリーン千葉中央」4階
2,680万円
 茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
約90㎡のゆとりと明るいリビングが魅力の3LDK「コスモ茅ヶ崎プレシオ」9階
1,980万円
 横浜市
横浜市
緑豊かな住環境と広々とした3LDK「三保ガーデン」
3,580万円
 北区
北区
築浅で最新の設備が満載!駅チカ2LDK物件「プレシスヴィアラ田端」9階
7,870万円
ハザードマップとは?

ハザードマップは主に「災害リスクの可視化や危険度の把握」を目的としており、災害の種類ごとに詳細な被害想定を示します。一方、防災マップは「避難場所や避難経路などの情報提供を通じて、安全な避難行動を支援」することを目的としているという違いがあります。
 栗栖
栗栖安全な暮らしを実現するためには、これらの点を理解して、マンション購入や日常の防災対策において両者を適切に活用することが大切です。
参考:大阪狭山市「【第10回】ハザードマップと防災マップの違いは?」
ハザードマップとは
ハザードマップとは、台風などの豪雨による浸水被害や土砂災害、地震時の揺れ、津波などの自然災害が起こった際に、どの地域がどの程度の被害を受ける可能性があるかを示した地図のことです。
被害が予想される区域や浸水の深さ、揺れの強さ、津波の到達時間などの情報が視覚的に示されており、事前にリスクを把握して災害への備えを強化するための重要なツールです。災害の種類ごとに作成され、国や自治体によって公開されています。
ハザードマップは専門家による分析などを集約して作成された地図です。全国的には「洪水・内水・土砂災害・高潮・津波」の5種類があり、これらをまとめて確認できる「重ねるハザードマップ(国土交通省運営)」があります。さらに、地域によっては「火山・ため池・地震」のハザードマップも作成されています。



ここでは、8種類のハザードマップを紹介しましょう。
参考:国土交通省「ハザードマップポータルサイト 重ねるハザードマップ」
参考:東京都防災ホームページ「火山ハザードマップ・火山防災マップ」
洪水ハザードマップ
洪水ハザードマップは、豪雨や河川の氾濫が起きた際にどの地域がどれだけ浸水するかを可視化した地図であり、以下のような情報が把握できます。
- 浸水想定区域
- 浸水深と浸水継続時間
- 指定緊急避難所
- 家屋倒壊等氾濫想定区域
これらの情報から特に注意したいのは「家屋倒壊等氾濫想定区域」です。



想定される最大の降雨により氾濫した河川によって、家屋が流失・倒壊する危険性の高い区域のため早期の避難が必要です。
内水ハザードマップ
内水ハザードマップは「下水道や小規模河川が豪雨によりあふれた際」に、どこまでエリアが浸水するかを示した地図です。特に都市部においては重要なマップであり、洪水ハザードマップでは浸水しないエリアでも内水によって深く浸水することがあります。主に以下の情報を読み取ることが可能です。
- 内水浸水想定区域
- 浸水する深さ(内水のみ)
- 過去の浸水実績や地形・排水設備の状況
- 指定緊急避難所



雨の降り方や周囲の状況の違いによって、マップ内で浸水が想定されていなくても実際には浸水が発生することもあるため、豪雨時には想定されていない地域も注意が必要です。
土砂災害ハザードマップ
土砂災害ハザードマップは、大雨や地震によって発生する「土石流・がけ崩れ・地すべり」などの、土砂災害のリスクが高い地域や、避難に役立つ情報をまとめたマップです。
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)・特別警戒区域(レッドゾーン)の表示
- 災害種別(土石流、崖崩れ、地すべり)ごとの危険箇所の明示
- 指定緊急避難所



土砂災害ハザードマップには、各種イエロー・レッドゾーンや地すべりのエリアが表示されていて、これらの中に自宅のある方は早期な避難が重要です。
高潮ハザードマップ
高潮ハザードマップは、低気圧や台風などによる高潮が発生した際に予測される浸水区域や浸水の深さ、浸水継続時間などを地図上に示し、迅速に避難行動を可能にします。
- 高潮浸水想定区域
- 浸水深と浸水継続時間
- 指定緊急避難所
- 想定条件の明示
実際に高潮は津波よりも被害エリアが広く、見逃してはならないハザードマップです。



津波ハザードマップでは浸水しないエリアでも高潮なら床上浸水することがあるため、しっかり確認しておきましょう。
津波ハザードマップ
津波ハザードマップは、海溝型地震の揺れによって発生する津波の浸水範囲や浸水深、避難場所や避難経路などを示しています。住民が海溝型地震後に津波を避けて安全に避難できるように作成されています。津波ハザードマップには、津波に備えて避難計画を立てる際に必要とされる以下の情報が記載されています。
- 津波浸水想定区域
- 浸水深の表示
- 津波到達時間や浸水時間
- 指定緊急避難所
- 警報発表時の対応や避難ルール
津波は、主に海溝型地震(海の中の地震)によって発生して陸地を襲う災害です。「直ぐに高い場所に逃げること」は誰もが知っている対策でしょう。



そのため、普段から逃げる場所をしっかり把握しておくことが重要です。
火山ハザードマップ
火山ハザードマップは、火山の噴火によって発生する複数の現象(溶岩流、火砕流、融雪型火山泥流、大きな噴石、降灰、降灰後の土石流など)による被害のリスク範囲を地図上に示し、火山災害から住民の安全を守るための防災情報を提供します。
- 想定火口範囲
- 過去の災害実績
- 避難計画や防災対応の基礎資料
- 防災情報の付加(火山防災マップ)
火山ハザードマップは、火山のある地域にて作成されています。例えば東京都では伊豆大島・新島・神津島・三宅島・八丈島・青ヶ島などの火山ハザードマップが掲載されています。



原則的にそのエリアの住民向けの情報ですが、火山活動時には旅行者も参考にすると良いでしょう。
ため池ハザードマップ
ため池ハザードマップは、ため池が長期に渡る大雨や急激な豪雨、地震などによって決壊した場合に想定される浸水区域や深さ、指定避難場所を示しています。迅速かつ的確な避難行動を災害時に促し、二次被害の回避や被害軽減が可能です。
- 浸水想定区域
- 浸水深の表示
- 歩行困難度の表示
- 指定緊急避難所



これらの情報は地域住民がため池の決壊リスクを示していて、ため池が決壊しても被害に遭わないように作成されています。
地震ハザードマップ
地震ハザードマップは、地震発生時に想定される揺れの強さや液状化の危険度、火災や倒壊などの住宅被害の可能性を示すマップです。住民が被害のリスクを理解し事前の備えや避難行動に活躍します。
- 揺れやすさ(震度)
- 液状化危険度
- 地域の危険度
- 指定緊急避難所
これらの情報から住民は地域の地震リスクを把握して、耐震対策や家具の固定、避難計画の作成を進められます。



エリアにおいて作成されており、場所によっては詳しい地震ハザードマップを確認できないこともあります。
ハザードマップはどんな時に使うのか


ハザードマップは自然災害が発生した場合や災害リスクが高まった時に迅速&適切な行動を取るのに役立つ重要な防災ツールです。自治体や個人では、以下のようなケースや目的で利用されています。
参考:国土交通省「水害ハザードマップの利活用事例集」
災害発生前|備えのための情報収集
ハザードマップを確認して平時から自宅や職場、学校周辺の災害リスクを具体的に知っておけば、「家具の固定」「非常持ち出し袋の準備」「備蓄品の準備」「家族による連絡方法や避難場所の相談」が可能となり、自分や家族の避難計画の策定に利用できます。
災害発生時|緊急避難に活用
ハザードマップを確認すると、危険な個所を避けた安全な避難行動が可能になります。実際に洪水や地震によって、土砂災害や浸水、津波などの災害が起きた際に自分が居る場所の被害がどの程度想定されているのかが確認できます。
自治体や企業の防災計画・対策作成に利用
ハザードマップは、地域による防災計画を策定する際や、従業員の安全確保に活用が可能です。例えば建設業ならハザードマップの情報をもとに、リスクの高い場所への活動を制限したり、介護施設では「レベル3:高齢者等避難」が発表された際に、指定避難所まで戸惑うことなく避難ができるように災害対応を強化したりする事例もあります。
避難訓練や防災教育の教材として
ハザードマップは、学校や地域の防災講座、災害図上訓練(DIG)や避難所運営ゲーム(HUG)などで活用され、参加者の防災意識をアップしたり災害時にリアルタイムで避難情報や危険区域の通知を受け取ったりできます。
デジタル技術と連携したリアルタイム活用
ハザードマップは、特別な設備や専用の防災システムがなくても、誰もが持っているスマートフォンに防災アプリとして組み込むことができます。これにより、災害時にでもリアルタイムで避難情報や危険区域が通知されるなど、住民一人ひとりの状況に応じた支援に活用できます。
ハザードマップと防災マップの違い
ハザードマップは、台風や地震、津波、高潮など、あらゆる自然災害による被害リスクを示しており、災害の発生しやすい場所や被害予測が把握できます。
一方 防災マップの主な目的は、災害発生時に具体的にどう行動すればよいかを示し、住民の安全確保や避難行動を支援することです。そこで、災害種別を問わず、災害が発生した際に安全に避難するために必要となる避難場所や避難経路、救急施設などの防災関連施設の位置を示しています。



つまり、ハザードマップと防災マップとの違いは以下のようにまとめられます。
- ハザードマップ: 災害リスクの見える化。どこが危険かを示している。
- 防災マップ: 災害発生時の具体的な行動計画。地域住民がどのように避難、対応するかを示している。
そのため、防災マップはハザードマップの情報をもとに作成されることが多く、両方を活用することで災害対策がより効果的になるでしょう。
ハザードマップの見方と使い方


ハザードマップは自然災害のリスクを視覚的に示した重要な防災ツールですが、その情報を正しく理解し活用することが、防災において何より大切です。ここではハザードマップの基本的な見方と使い方を解説します。
参考:国土交通省「ハザードマップポータルサイト 重ねるハザードマップ」
色や記号でリスクエリア(危険区域)を確認
ハザードマップ上の色や記号を見て自宅や職場などに、どの程度災害リスクがあるのかを確認します。例えば、洪水ハザードマップでは色によって浸水深がわかりますし、土砂災害ハザードマップでは色のある場所が危険が想定されている区域です。



特に特別警戒区域(赤色の表示)になっていれば迅速な避難が必要です。
避難場所の確認
ハザードマップには指定避難所が掲載されていますが、水害・地震・津波など災害種別によって利用制限があります。そのため、場所のみを確認するのでなく、該当する災害において利用可能であるか事前に確認しておきましょう。



また、避難所までの移動ルートもしっかり確認し、できれば平時に歩いて避難所まで移動するのがおすすめです。
デジタル版でリアルタイムの情報も確認可能
現在では多くの自治体がWEBサイトやスマホアプリにてハザードマップを公開しており、災害発生時や気象情報と連動して最新の避難情報や危険エリアをリアルタイムで確認できます。



国土交通省の「重ねるハザードマップ」なら、スマホで全国をいつでも確認可能です。
マンション購入前にハザードマップでチェックしておくべきポイント


特に中古マンションの購入を検討している方にとって、ハザードマップは住まいの安全性を見極める上で欠かせない重要な資料です。自然災害のリスクを正しく把握し、安心して長く暮らせる住まい選びをするために、以下のポイントをしっかりとチェックしましょう。
参考:国土交通省「ハザードマップポータルサイト 重ねるハザードマップ」
参考:国土交通省「動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」
物件所在地の災害リスクを複数のハザードマップで確認する
気になるマンションを見つけたら、複数のハザードマップで災害リスクを確認しておきましょう。
例えば水害を想定した場合なら(洪水・内水・高潮・津波)の、4つのハザードマップを確認します。さらに、土砂災害ハザードマップで土砂災害が起きないか確認し、地震ハザードマップで大きな揺れがないかも知っておくべきでしょう。
このように、複数のハザードマップを見てどのような災害があるのか総合的に判断します。



特に中古マンションは建設当時と災害リスクの変化があるため、最新の情報をチェックすることが重要です。
警戒区域(イエローゾーン)・特別警戒区域(レッドゾーン)の有無を確認
特に土砂災害については、警戒区域(イエローゾーン)や特別警戒区域(レッドゾーン)の範囲にある場合は、災害時に被害が起きる可能性が高まります。



新築時には指定されていなかったのに、現在では指定されているケースもあり得るため、中古マンション購入時は土砂災害の指定区域に入っていないかを確認しましょう。
避難場所と避難経路の安全性の確認
ハザードマップには災害ごとの指定避難所が掲載されており、避難ルートも検討できます。
平時に物件からもっとも近い指定避難所までのルートを歩いて、冠水被害や斜面崩壊などが起きないかを確認し、ルート上に高いブロック塀があるなど安全面の確認は重要です。
ルート上の危険箇所は、実際に歩いて確認してみることでしか気づけない場合もあります。



物件を選ぶ際には、実際にルートを歩いてみて避難経路の安全性まで含めて確認することが大きなポイントです。
周辺施設や生活圏のリスクも確認する
自宅となるマンションだけでなく、子どもの学校や職場、よく利用するスーパーなどの商業施設や病院のように、日常における生活圏の災害リスクを確認すると安心して過ごせるでしょう。



特に子どもの通学路などは安全性に配慮が必要です。
ハザードリスクに応じた住まい選びの工夫を検討する
適切なマンションを見つけてハザードマップにて災害リスクが存在するエリアであっても上層階や防災設備や構造が丈夫なマンションを選ぶ方法があります。また、水災特約付の火災保険に加入して、安全性を高めることもできます。
過去の災害経験や地域の防災体制にも目を向けてみれば、防災訓練の実施や住民の防災意識が高まり、安心感のある地域づくりが進んでいる場所があるかも知れません。



このように、ハザードリスクに応じた住まい選びの工夫を検討すれば、より安全性の高い暮らしが期待できます。
まとめ


ハザードマップの種類や中古マンションを購入する際の、チェックしておくべきポイントなどを防災士目線で解説しました。
スムナラが紹介するマンションなら、自分でさまざまなハザードマップを探さなくても、担当者が関連するハザードマップを説明付きで紹介してくれます。そのため、時間の節約ができて必要な防災事項まで素早く把握できます。さらに、マンション近隣の状況を熟知した担当者から、防災訓練の実施時期や災害に対する相談窓口をお伝えすることも可能です。
中古マンションにて安全に暮らしていくために、ぜひハザードマップや防災情報を取り扱っているスムナラへお気軽にお問い合わせください。