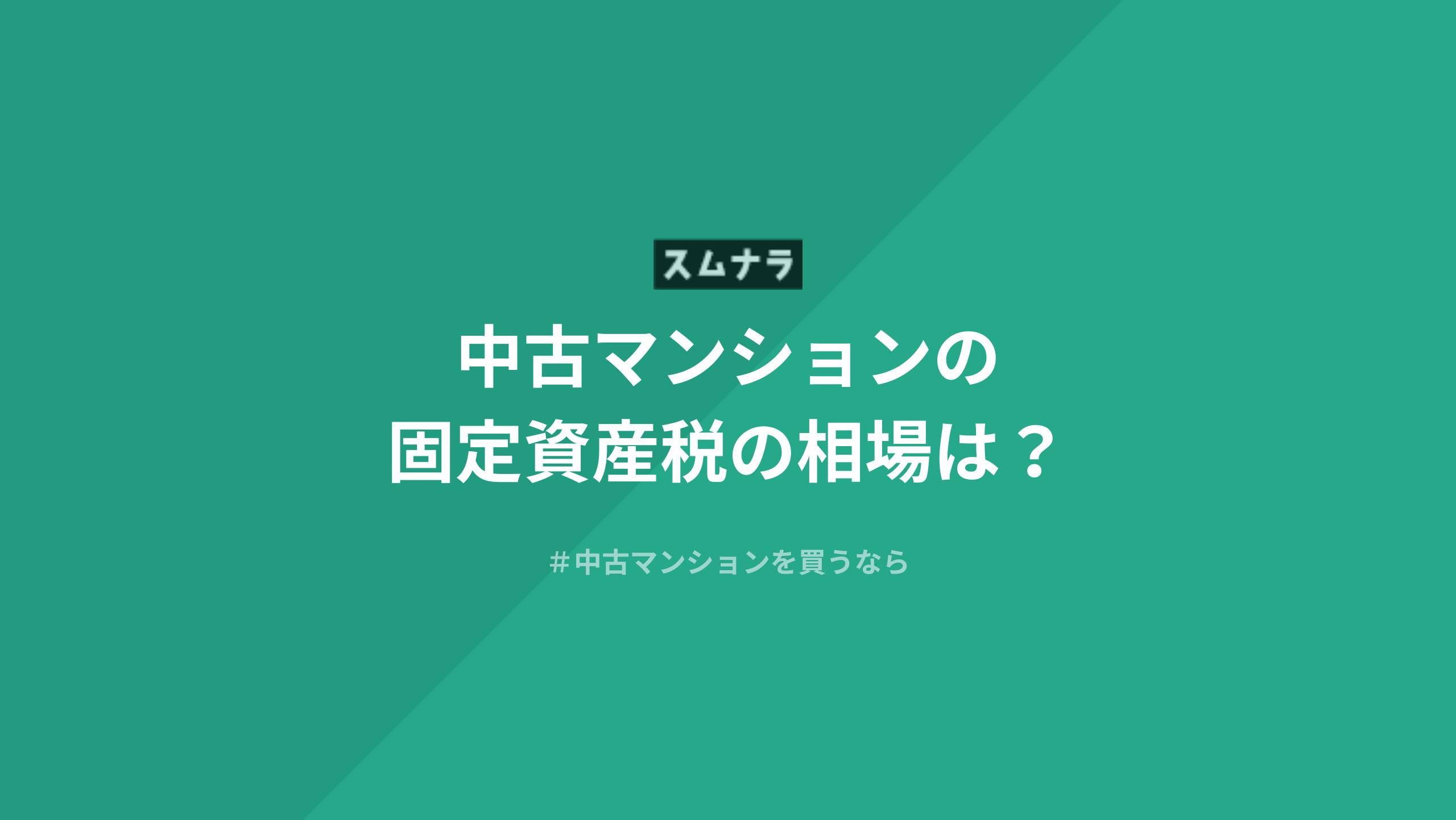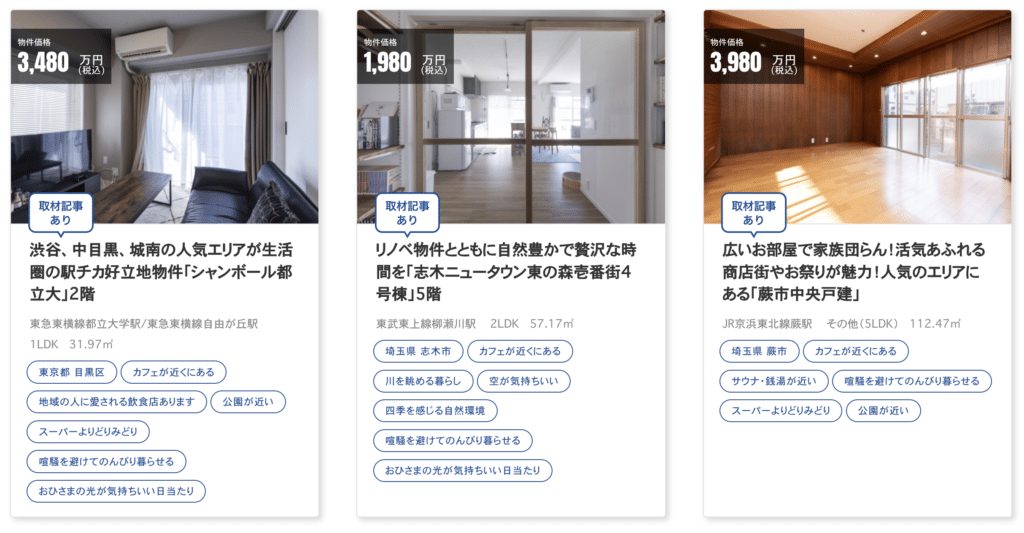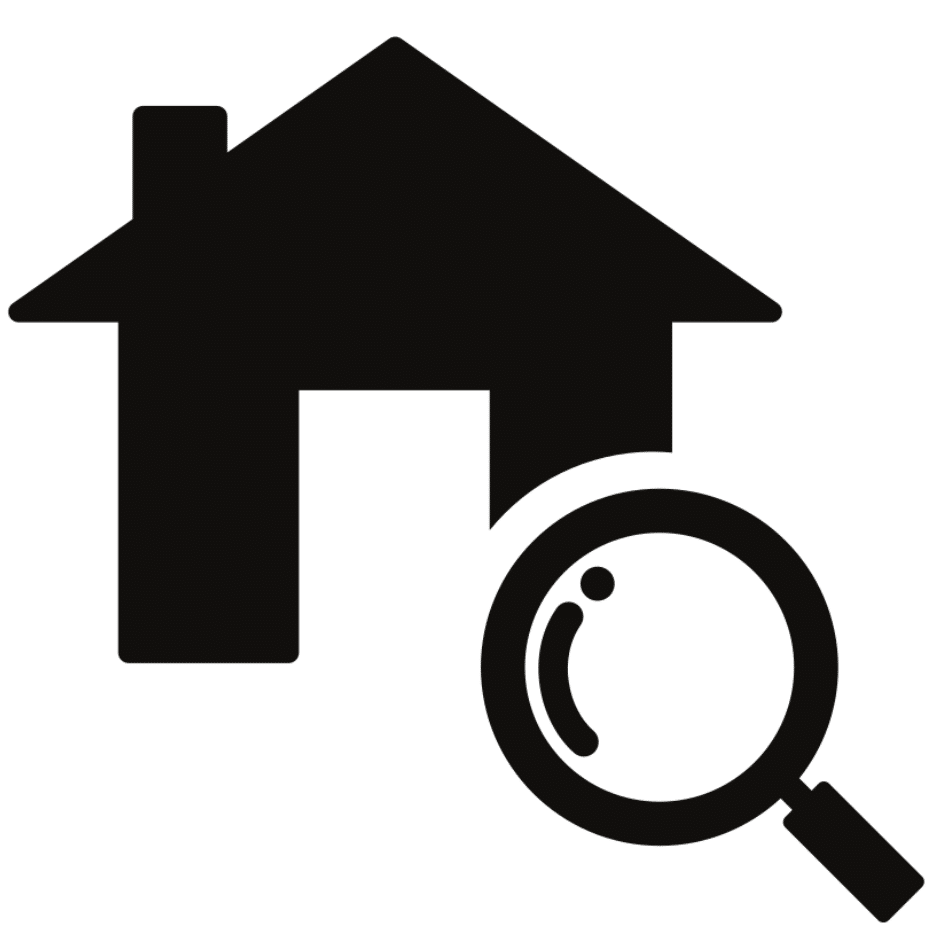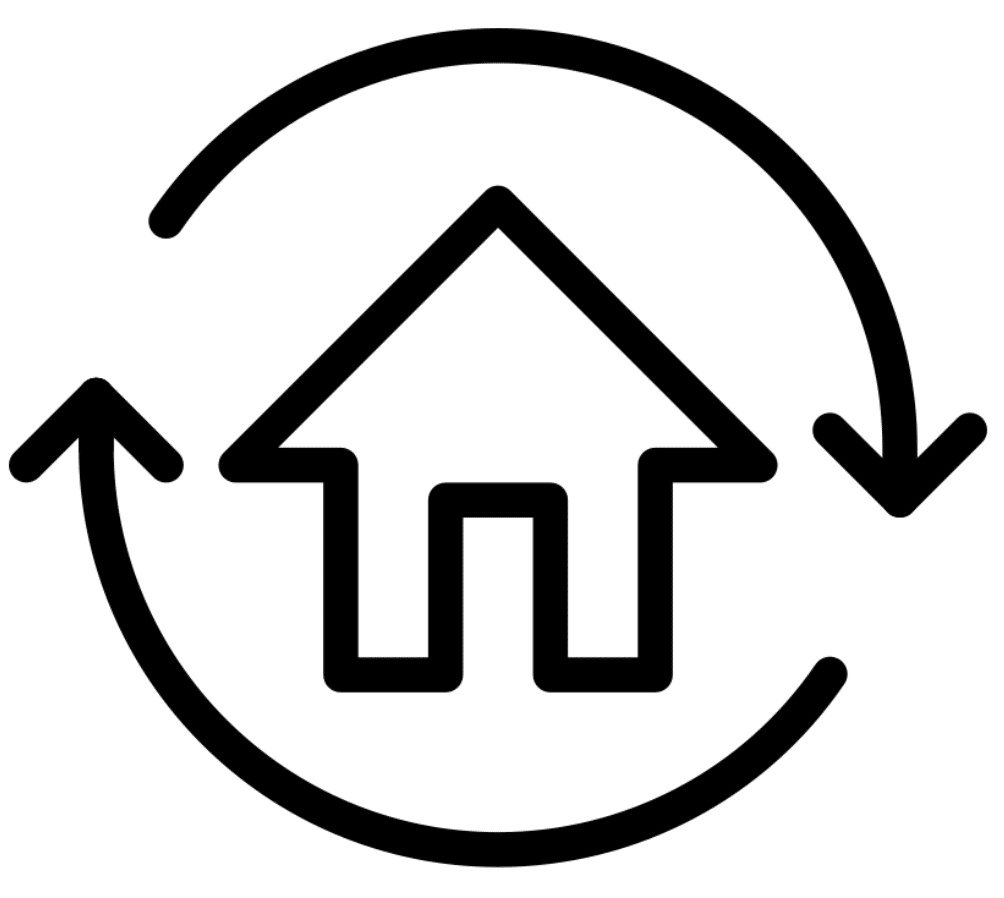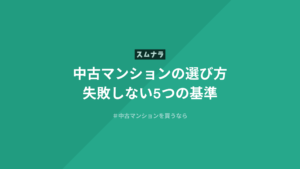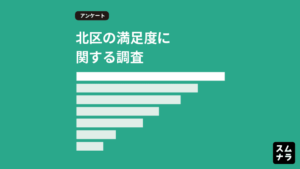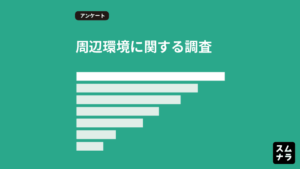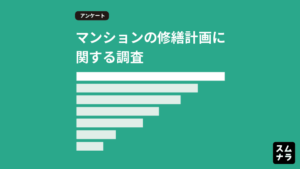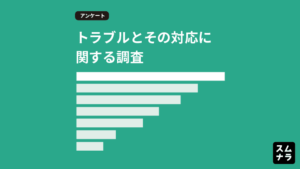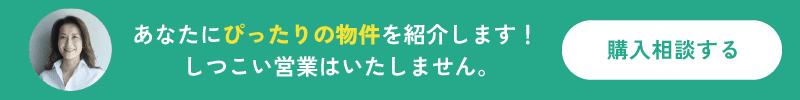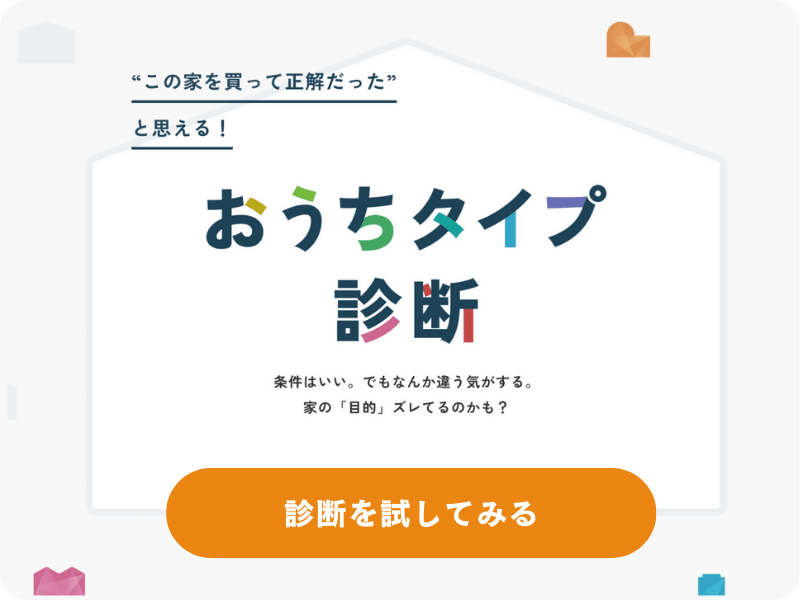「中古マンションの固定資産税ってどのくらいかかるの?」
「築年数によって税額がどれほど変わるの?」
そんな疑問をお持ちではないでしょうか。固定資産税は不動産を所有している限り毎年支払う税金ですが、その仕組みや計算方法がわかりづらいと感じる方も少なくありません。
固定資産税額は、土地や建物の評価額、築年数、軽減措置などさまざまな要因によって異なります。そこでこの記事では、中古マンションの固定資産税に焦点を当て、基本的な仕組みから築年数ごとの税額の違い、さらには軽減措置の活用方法まで詳しく紹介します。
この記事を読めば、固定資産税に関する疑問が解消し、中古マンションの購入計画や売却に役立つ知識が身につけられるでしょう。

宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社で実務を経験後、不動産ライターとして独立。
不動産賃貸・管理の経験を活かし、自身でもアパート・マンション等の不動産賃貸経営を行う。不動産売却(相続、共有持分、任意売却、買取、空き家etc)、不動産投資、不動産賃貸、不動産管理など、幅広い分野の執筆、監修をしている。
本記事の内容は2025年1月10日時点の情報に基づいており、不動産市場の状況や関連法規、税制などは将来変更される可能性があります。最新の情報については、公式の情報源をご確認ください。
無料オンラインセミナー
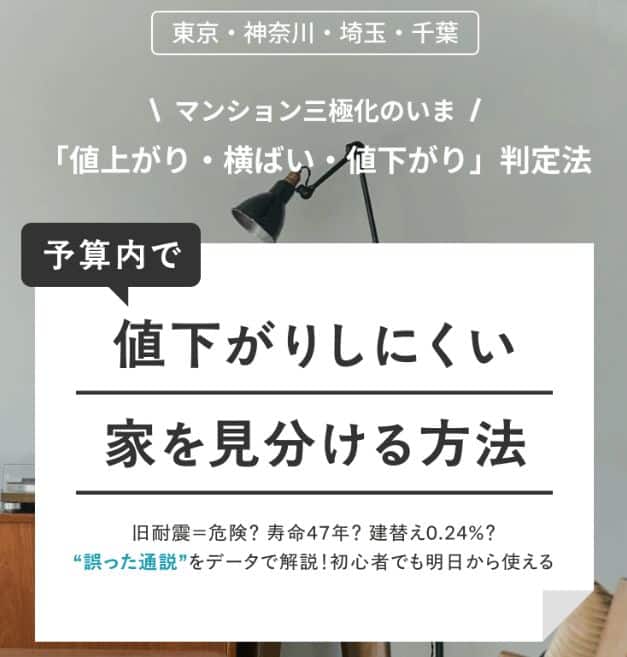
中古マンションを購入検討の方必見!
【セミナーの内容】
- 市場は「大吉・中吉・凶」の三極化
- 予算内で「中吉以上」を選ぶ方法
- 築年・立地・管理の3視点で探す
- 資産性・耐震性・寿命・建替えを解説
- 初心者歓迎・家族参加OK
- セールスなしで安心参加
固定資産税とは
固定資産税は、土地や建物といった不動産などを所有している人に課される地方税です。支払いは通常、年4回に分けて行うことが多いですが、市町村によっては一括で支払うことも可能です。
なお、中古マンションを購入する際、初年度の固定資産税については、購入した日から年末までの期間分を日割りで計算し、買主が負担するケースが一般的です。この取り決めは物件によって異なるため、契約時に不動産会社に確認することが大切です。
毎年1月1日に所有する不動産に課される税金
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している人が課税対象となり、その年度分の固定資産税を支払う義務が発生します。
この税金は、市区町村が提供する公共サービスの財源として使われるため、各自治体によって税率や計算方法に若干の違いがあります。一般的な固定資産税の税率は課税標準額の1.4%ですが、一部の市町村では税率が異なる場合もあります。
 松元
松元不動産の購入や売却を検討している場合、所有時点での税負担をしっかり把握しておくことが大切です。
固定資産税評価額は新築と中古で違う
建物の固定資産税評価額は、新築と中古で計算方法が異なります。新築では、再建築に必要な費用(再建築価格)を基準に評価額が決まり、一般的に請負工事費の50~60%が目安とされています。
一方、中古マンションでは築年数に応じた「経年減価補正率」が適用され、価値の減少を反映した評価額が算出されます。例えば、築20年では補正率が0.5054となり、新築時の評価額の約半分に下がる計算です。



中古物件の場合、購入前に評価額が確定しており、不動産所有者の同意があれば、市区町村の課税台帳で確認可能です。
参考:法務局 経年減価補正率表
固定資産税がかからないケース
固定資産税がかからないケースにはいくつかの条件があります。まず、土地や建物の「課税標準額」が一定額を下回る場合です。具体的には、土地は30万円、建物は20万円が免税点であり、これを下回ると課税されません。
また、1月1日の課税基準日時点で存在しない建物も対象外となります。



例えば、12月末までに建物を解体した場合、翌年の課税が免除されます。
マンションの固定資産税の相場は10~30万円程度
一般的にマンションの固定資産税は、年間で10~30万円程度が目安です。ただし、物件の所在地や条件によって固定資産税評価額が異なるため、同じマンション内であっても税額に違いが生じることがあります。
中古マンションは築年数に応じて経年減価補正率が適用されるため、評価額が低くなり、税額も10~20万円程度と抑えられる傾向にあります。



これらの違いを踏まえて、購入時に税額を確認することが大切です。
無料オンラインセミナー
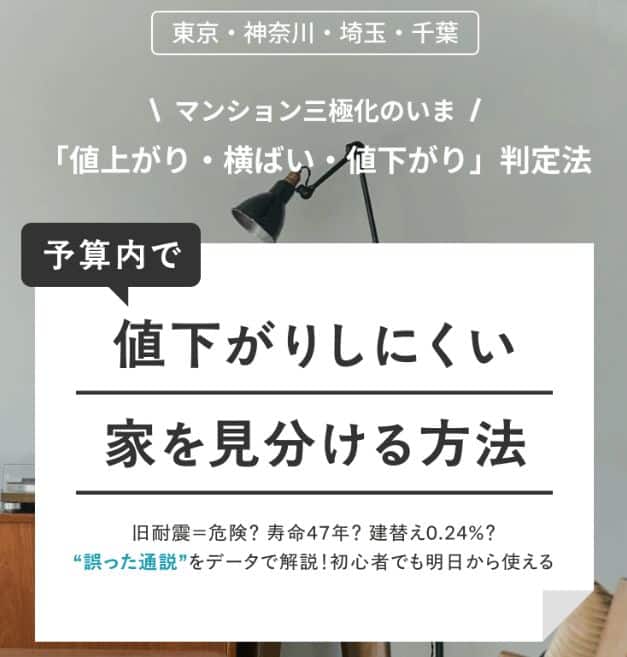
中古マンションを購入検討の方必見!
【セミナーの内容】
- 市場は「大吉・中吉・凶」の三極化
- 予算内で「中吉以上」を選ぶ方法
- 築年・立地・管理の3視点で探す
- 資産性・耐震性・寿命・建替えを解説
- 初心者歓迎・家族参加OK
- セールスなしで安心参加
マンションの固定資産税の軽減措置の種類
マンションの固定資産税には、土地や建物の評価額が軽減される制度が用意されています。これらの軽減措置を活用することで、対象となるマンションの固定資産税額を抑えることが可能です。適用条件を満たすかどうかによって、同じ地域や建物内でも税額に差が出る場合があります。ここからは、マンションの固定資産税に関する主な軽減措置の内容について詳しく解説していきます。
土地
土地の軽減措置は、「住宅用地特例」とよばれる制度で、居住用建物が建っている土地を対象に、面積に応じて固定資産税評価額が軽減されます。この制度では、200平米以下の部分については評価額が6分の1、200平米を超える部分については3分の1に軽減されます。
また、この特例はマンションの築年数に関係なく適用され、2024年現在では適用期間の制限がありません。



そのため、所有する土地の評価額を確認し、この軽減措置を活用することで、固定資産税の負担を抑えることができます。
建物
建物に適用される軽減措置は、「新築住宅特例」とよばれ、一定の条件を満たす新築住宅について、床面積120平米までの部分の固定資産税評価額が2分の1に軽減される制度です。この措置を受けるための主な条件は以下のとおりです。
- 2026年3月31日までに新築された住宅
- 床面積が50平米以上280平米以下
- 居住用部分が全体の床面積の2分の1以上
軽減措置の適用期間は、住宅の種類によって異なります。一般的な住宅の場合は3年間、3階建て以上の耐火・準耐火構造の場合は5年間、さらに認定長期優良住宅に該当する場合は最大7年間適用されます。
例えば、3階建ての耐火構造マンションで長期優良住宅の認定を受けた場合、7年間にわたって評価額が2分の1に軽減されるため、税負担を大幅に減らすことが可能です。



適用条件を確認し、制度を活用することで固定資産税の負担を効果的に軽減できます。
タワーマンション
2018年以降に建設された20階以上のタワーマンションでは、2017年の税制改正によって固定資産税の算出方法に特例措置が導入されました。この改正により、階層ごとに固定資産税評価額が補正される仕組みが適用されたため、高層階ほど税額が高く、低層階では税負担が軽減されるケースが生じています。
タワーマンションでは、高層階は眺望や日当たりの良さ、プライバシーの確保といった理由から市場価値が高くなりやすい傾向があります。この市場価値の違いが、税負担の公平性を求めた改正の背景にあるのです。
改正では、「階層別専有床面積補正率」という新たな指標が導入され、階数に応じた評価額の補正が行われます。



これにより、高層階の住民は従来よりも高い固定資産税を負担する一方、低層階の住民は税額が抑えられるようになりました。
バリアフリー改修工事
バリアフリー改修工事を行った住宅に対しては、翌年1年間に限り、建物の固定資産税評価額(100平米までの部分)が3分の1に減額される特例が適用されます。



この軽減措置は、特に高齢者や障がい者が住む住宅での負担を軽減するための制度です。
適用を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
適用条件
まず住宅の条件として、新築から10年以上経過していることが求められます。また、賃貸住宅は対象外で、改修後の床面積が50平米以上280平米以下である必要があります。さらに、居住部分が全体の2分の1以上を占めることも要件に含まれます。
次に居住者の条件として、対象となるのは65歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、もしくは障がい者です。
これに加え、工事費用が補助金を除いて50万円以上であることが求められます。なお、この特例は2026年3月31日までに改修工事が完了していることが条件です。
対象となる改修工事
軽減措置の対象となる工事は、通路の拡張や階段の勾配緩和、浴室やトイレの改良、手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、出入口ドアの改良などです。これらは安全性を高め、居住者が安心して暮らせる環境を整えるための工事が含まれます。
手続きと書類
軽減措置を受けるには、工事完了後3カ月以内に、市区町村の窓口に申請が必要です。申請時には、以下の書類が求められます。
- 固定資産税減額申告書
- 介護保険証など、対象者であることを証明する書類
- 改修工事費用がわかる書類
- 補助金を受けた場合は、その金額が記載された書類
必要書類は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。この制度を活用することで、バリアフリー改修を行った際の税負担を大幅に軽減することが可能です。
省エネ改修工事
省エネ改修工事を行った住宅は、条件を満たすことで固定資産税が減額されます。対象は2014年(平成26年)4月1日以前に建築され、居住部分が全体の1/2以上を占める住宅です。工事は2022年(令和4年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日までに実施され、窓の断熱改修が必須となります。加えて、床、天井、壁の断熱改修や省エネ機器の設置が条件に含まれる場合があります。
工事費用は、補助金等を除いた額が60万円を超える必要があり、改修後の床面積が50平米以上280平米以下であることも求められます。なお、他の減額措置と併用はできません。
減額は翌年度の固定資産税で、床面積120平米分まで3分の1が軽減されます。



工事完了後3カ月以内に必要書類を自治体へ提出することで申請が可能です。制度を活用して税負担を軽減しましょう。
【築年数別】中古マンションの固定資産税の計算方法
ここでは、築年数によって固定資産税額がどのように変化するかを具体的にシミュレーションします。築年数が経過すると、建物の固定資産税評価額が減少します。



この減額は、経年劣化に応じて行われるもので、特に建物部分が影響を受けます。
例えば東京都では、経年劣化に基づいて建物の評価額を調整する「経年減価補正率」が以下のように定められており、これにより築年数が古いほど税額が軽減されます。
| 経過年数 | 減価率 |
| 築1年 | 0.9579 |
| 築2年 | 0.9309 |
| 築3年 | 0.9038 |
| 築4年 | 0.8803 |
| 築5年 | 0.8569 |
| 築6年 | 0.8335 |
| 築7年 | 0.8100 |
| 築8年 | 0.7866 |
| 築9年 | 0.7632 |
| 築10年 | 0.7397 |
| 築15年 | 0.6225 |
| 築20年 | 0.5054 |
| 築25年 | 0.3992 |
| 築30年 | 0.3059 |
| 築35年 | 0.2345 |
| 築40年 | 0.2089 |
| 築45年以上 | 0.2000 |
参考:東京法務局「経年減価補正率表(非木造建物減価補正率)」
ここでは、土地の価格を3,000万円、建物の価格を1,000万円と仮定して、築年数ごとの固定資産税の変化を具体的に見ていきましょう。
築10年
築10年の中古マンションの経年減価補正率は「0.7397」なので、この数字を用いて計算します。
- 土地の固定資産税:3,000万円×1.4%×1/6=70,000円
- 建物の固定資産税:1,000万円×0.7397×1.4%=103,558円
- 固定資産税合計額:70,000円+103,558円=173,558円
築20年
築20年の中古マンションの経年減価補正率は「0.5054」なので、この数字を用いて計算します。
- 土地の固定資産税:3,000万円×1.4%×1/6=70,000円
- 建物の固定資産税:1,000万円×0.5054×1.4%=70,756円
- 固定資産税合計額:70,000円+70,756円=140,756円
築30年
築30年の中古マンションの経年減価補正率は「0.3059」なので、この数字を用いて計算します。
- 土地の固定資産税:3,000万円×1.4%×1/6=70,000円
- 建物の固定資産税:1,000万円×0.3059×1.4%=42,826円
- 固定資産税合計額:70,000円+42,826円=112,826円
築40年
築40年の中古マンションの経年減価補正率は「0.2089」なので、この数字を用いて計算します。
- 土地の固定資産税:3,000万円×1.4%×1/6=70,000円
- 建物の固定資産税:1,000万円×0.2089×1.4%=29,246円
- 固定資産税合計額:70,000円+42,826円=99,246円
築年数が経過するほど建物の評価額が減少し、建物部分の固定資産税額が軽減されます。その結果、マンション全体の固定資産税額も築年数に応じて低くなります。
この計算例を基に、購入や所有時の税負担を検討する際の参考にしてください。
まとめ
本記事では、中古マンションの固定資産税について、基本知識から具体的な計算方法まで幅広く解説しました。築年数に応じた評価額の変化や、土地・建物それぞれの軽減措置の適用条件についても紹介しましたので、固定資産税の全体像がつかめたのではないでしょうか。
これで、購入後の税額を予測しやすくなり、固定資産税に関する計画を立てる手助けができたなら幸いです。適切な知識を持つことで、より安心して中古マンションの購入・維持を進めることができます。
この記事を活用して、固定資産税対策を行い、長期的な不動産運用を成功させていきましょう!