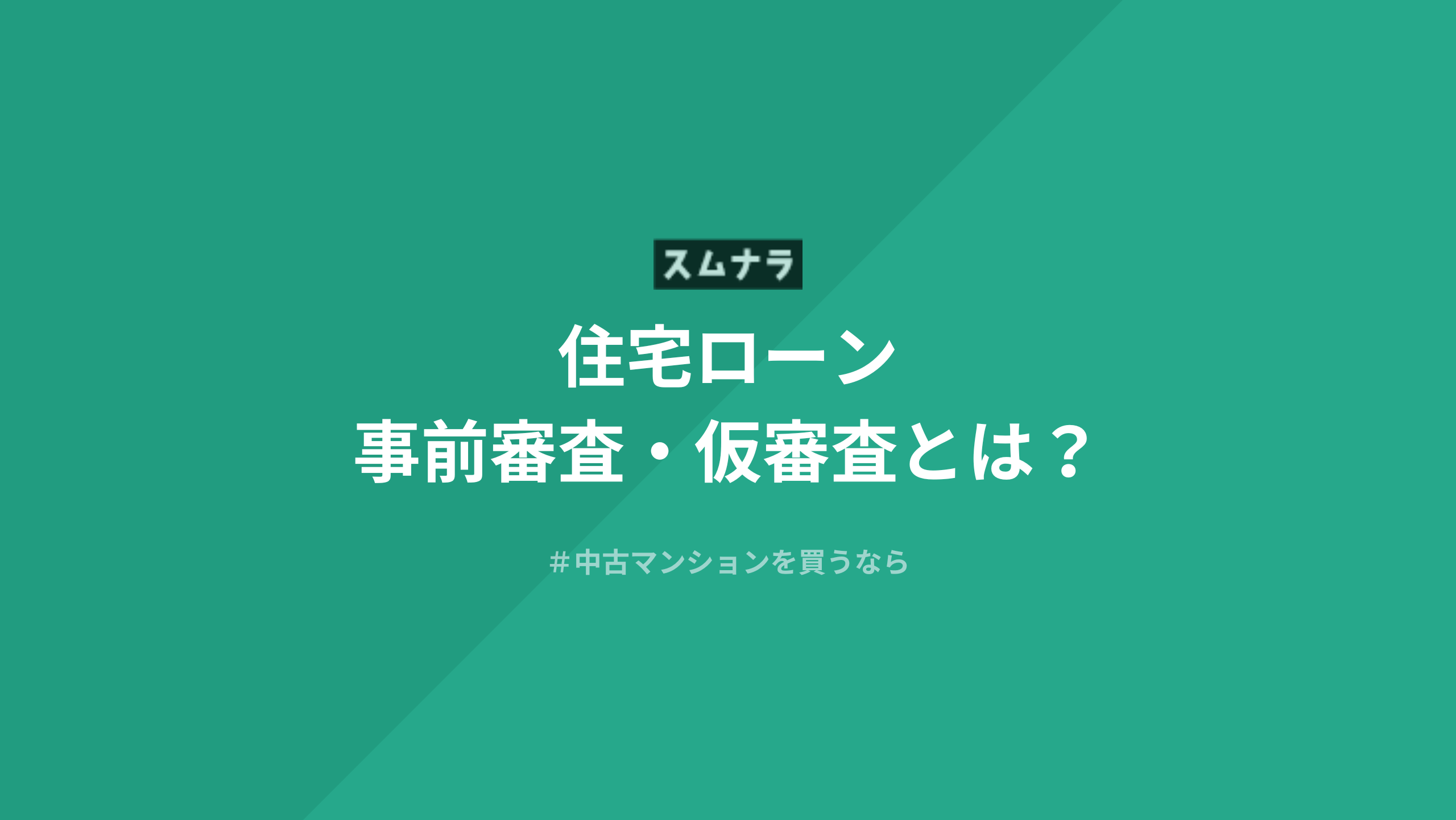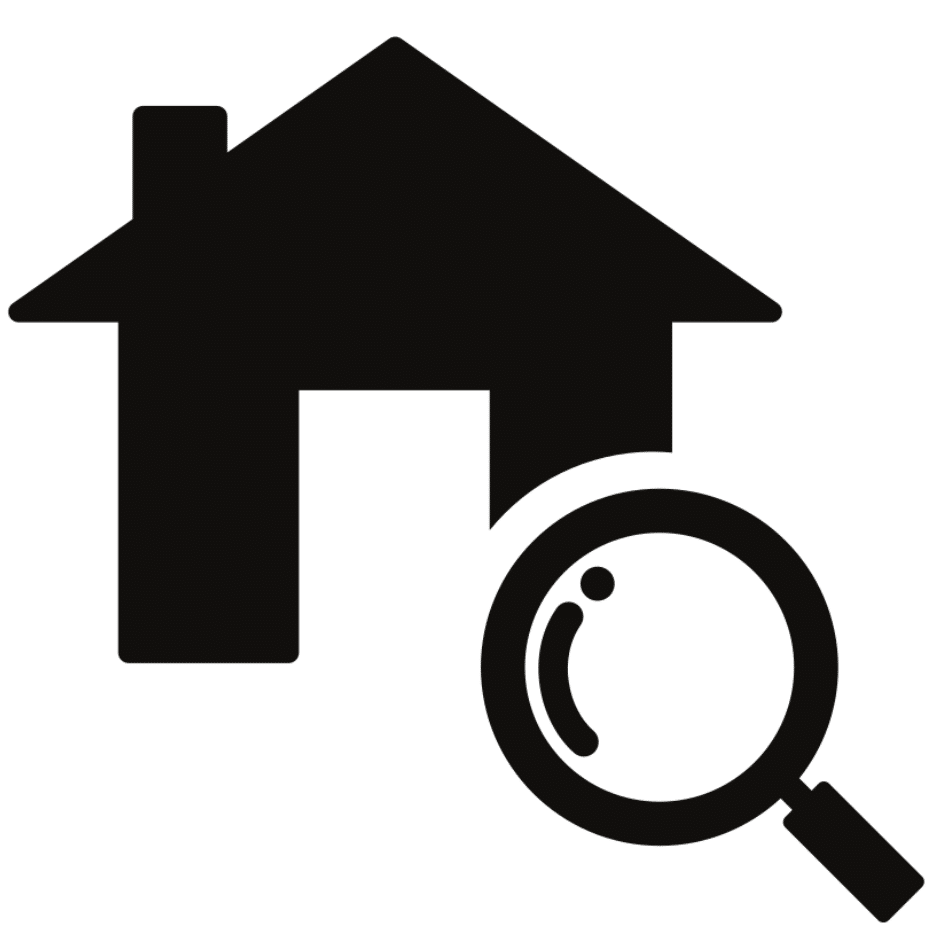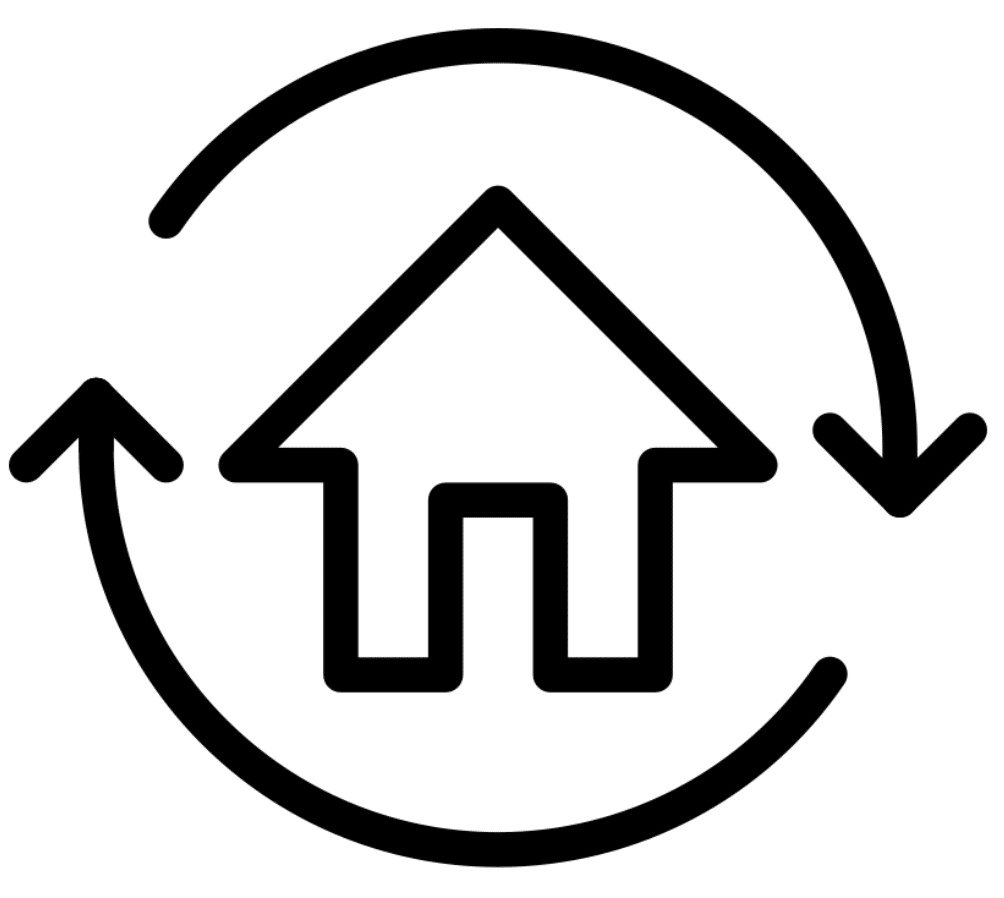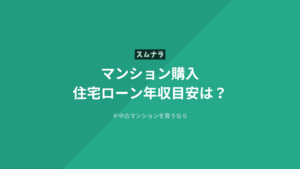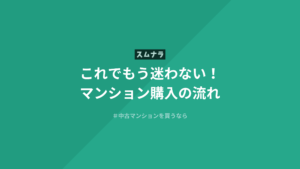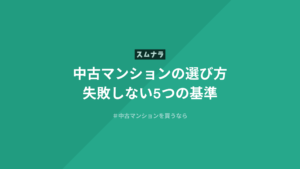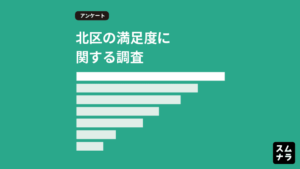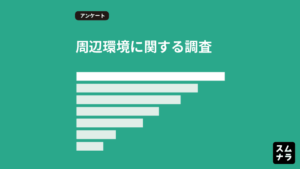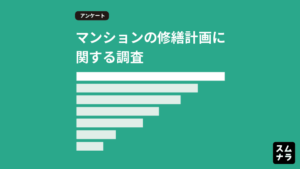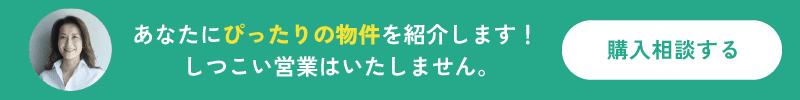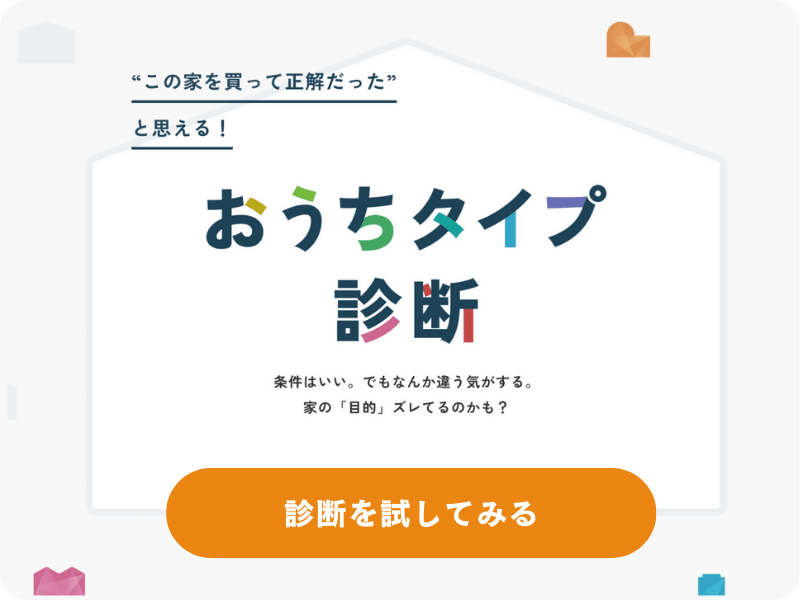初めて住宅ローンを申し込む場合、不安がつきものです。
「審査に落ちないための方法が知りたい!」
「住宅ローン審査に落ちたら、どうしたらいいの?」
「事前審査と本審査の違いは?」
など、わからないことも多いでしょう。
ましてや、住宅の価格や政策金利は上がっています。年収が高くないと審査が通らないのでは?などと心配になるかもしれません。
そこで、この記事では、住宅ローン事前審査・仮審査とはどのようなものか、審査基準や落ちた時の対処法などを解説します。
住宅ローンの審査基準を一言でいうと、「現時点で将来に渡って返済できる能力があるかどうか」です。この点をそれぞれの審査に必要な書類で示すことができればローンを組むことはできます。もし今はその条件を満たせない場合でも、しっかり対策をしておけば、しかるべきタイミングに審査を通すことは可能なのです。この辺りのサポートは不動産仲介会社によって異なるため、その点も後半で詳しく解説しています。

宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
早稲田大卒。マスコミ広報宣伝・大手メーカーのWebディレクター・不動産仲介業を経て、ライター業・不動産投資に従事。宅建士の業務の他、物件写真撮影とレタッチ・販売賃貸図面作成・重説契約書作成まで対応していた。実務経験をもとに、不動産の購入・売却、住まいの知恵、暮らしの法令、税金・法律などの幅広いテーマの執筆を行う。法令に則しながら、時流や現状も踏まえた解説を心掛けている。
本記事の内容は2025年1月16日時点の情報に基づいており、不動産市場の状況や関連法規、税制などは将来変更される可能性があります。最新の情報については、公式の情報源をご確認ください。
無料オンラインセミナー
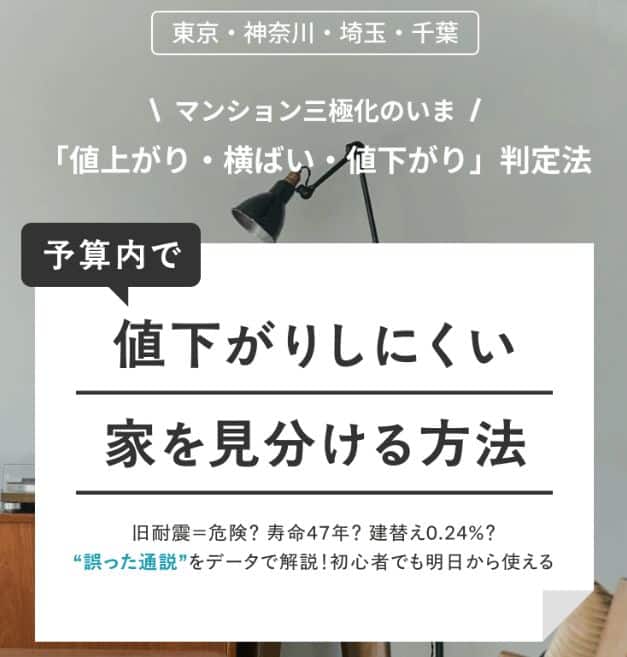
中古マンションを購入検討の方必見!
【セミナーの内容】
- 市場は「大吉・中吉・凶」の三極化
- 予算内で「中吉以上」を選ぶ方法
- 築年・立地・管理の3視点で探す
- 資産性・耐震性・寿命・建替えを解説
- 初心者歓迎・家族参加OK
- セールスなしで安心参加
住宅ローンの事前審査・仮審査とは?
住宅ローンは事前審査(仮審査)と本審査の2段階で、融資を行うかを決める仕組みとなっています。審査を1度に済ませずに、2回にしているのはなぜなのでしょうか。
事前審査・仮審査の違い
2つの審査には以下のような違いがあります。
事前審査:融資を希望する人(買主)がローンを組めるかの基本的なチェック
本審査:買主と物件に関する詳細な書類チェック
事前審査によって、買主は借入の大まかな目途を立てることができ、早い段階で物件を借り押さえできます。売主にとっても、物件購入の手続きが始まれば、資金計画の見通しが立つので好都合です。
一方金融機関にとっては、事前審査によってローンに通らない人に本格的な審査の労力を使わずにすみます。さらに本審査時に売買契約の写しを受け取っていれば、買主の購入意思の念押しにもなります。
 滋野
滋野2段階の審査は、買主・売主・金融機関の3者いずれにとっても都合のいいシステムなのです。
住宅ローンの審査の流れ
購入したい物件を決めたら、購入申し込みとともに、住宅ローンの事前審査に申し込みます。提出書類は申込書の他、本人確認書類・収入確認資料・物件の販売チラシなどです。
結果がわかるのは、平均して数日~1週間程度です。事前審査に通ったら、売買契約を締結します。
金融機関から購入資金を借入する場合、売買契約書の中には「融資利用の特約」や「融資条項」=ローン条項という項目が設けられています。これは、住宅ローンの本審査に通らなかった場合に売買契約が白紙になる旨の約束です。
続いて本審査では、本審査用申込書の他、団体信用生命保険申込書・勤務先確認書類・印鑑証明・売買契約書と重要事項説明書の写し・工事請負契約書の写し・土地や建物の登記簿謄本・土地の公図など多くの書類が必要となります。
本審査に通れば、土地・家の購入に関する決済や引き渡し・所有権の移転などの正式な取引が可能です。



なお、本審査の結果で融資総額の減額提案などがされ、資金計画を調整するようなケースもあります。


住宅ローンの事前審査(仮審査)における審査基準
金融機関は融資の際にまず何を重視するのでしょうか。一般的な印象では「収入」「勤務先の安定度」などと考えるかもしれませんが、実はそうではありません。
国土交通省の令和5年の調査結果では、融資の際に考慮する項目の比率は以下のようになっています。
- 「完済時年齢」(98.5%)
- 「健康状態」(96.6%)
- 「借入時年齢」(96.0%)
- 「年収」(94.0%)
- 「勤続年数」(93.6%)
- 「返済負担率」(92.0%)
- 「担保評価」(91.8%)
金融機関は上記のようなさまざまな融資申請者の情報を見ながら、ようするに「融資したお金を将来継続して返済できるかどうか」を審査するのです。それぞれの条件の細かい基準は金融機関によって異なるため、いわば金融機関の数だけ審査基準があるというわけです。ここからは一般的な審査基準について解説していきます。
年齢
年齢は、完済時の年齢と借入時の年齢がチェックされます。現在主流となっている指標は、「最長80歳までに返済できる」です。また、借入時年齢は65~70歳未満が基準となります。
しかし近年、定年の年齢が流動化し、年金の支給も繰り下げが推奨されています。



80歳までの年限があまり短い状況での審査では、自己資金が多くなければ借入が難しい場合があるかもしれません。
無料オンラインセミナー
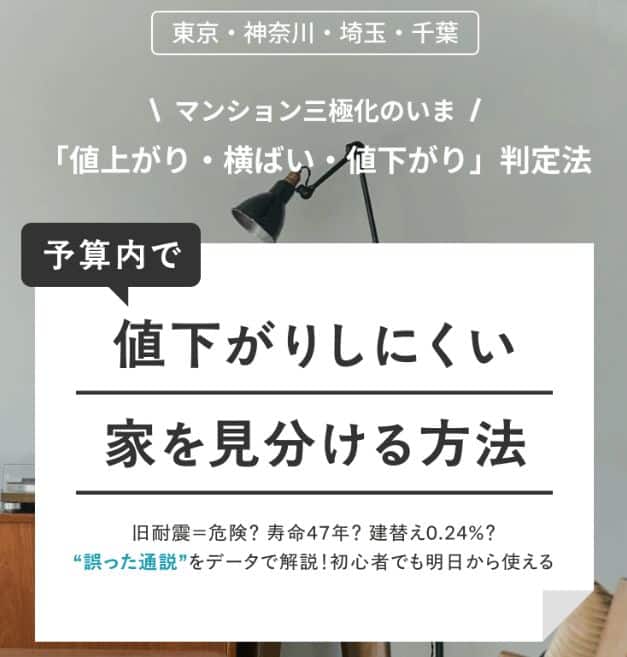
中古マンションを購入検討の方必見!
【セミナーの内容】
- 市場は「大吉・中吉・凶」の三極化
- 予算内で「中吉以上」を選ぶ方法
- 築年・立地・管理の3視点で探す
- 資産性・耐震性・寿命・建替えを解説
- 初心者歓迎・家族参加OK
- セールスなしで安心参加
健康状態
フラット35などを除き、ほとんどの金融機関が融資条件に「団体信用生命保険(団信)の加入が必要」となっています。
団体信用生命保険に加入していれば、ローンの名義人が亡くなるなど、もしものことがあった場合に残債の支払いは免除されます。団体信用生命保険に加入できなければ、ローン審査にも通らないことが多いので、過去の病歴や健康診断の状況、通院状況など健康状態に不安がある人は、注意が必要です。
健康状態を改善してから再度団信の審査を受けるか、団信加入の不要なフラット35の加入を検討しましょう。



また、最近では金利がやや高くなるものの、告知内容が緩やかで審査に通りやすい「ワイド団信」を扱う金融機関もあります。
担保評価
担保評価とは、融資の対象となった物件が、貸し付ける金額に見合う価値があるかどうかを示す指標です。下の表は住宅ローン審査落ちをしたことのある人の担保評価割合を住宅の種類と地域によって示したものです。中古物件で担保評価割合がやや多くなるのは、担保評価に対して借入希望額が多かったためと考えられます。
| 単位:% | 全国 | 首都圏 | 中京圏 | 近畿圏 |
|---|---|---|---|---|
| 注文住宅 | 16.3 | 22.1 | 9.2 | 13.9 |
| 分譲住宅 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 10.0 |
| 中古住宅 | 20.3 | 19.2 | 23.2 | 17.2 |
| リフォーム住宅 | 13.5 | 17.0 | 8.9 | 6.3 |
事前審査の場合、年収や勤続年数の細かい属性よりも、「借りられるかどうか・何年借りられて、問題なく返せそうか」という基礎的な部分が重視されます。この他に信用情報の問題や、他の借入状況などもチェックされます。
参考:国土交通省「令和5年度 民間住宅ローンの実態に関する調査」
事前審査・仮審査で落ちる理由
事前審査で問題となりやすいのが、信用情報です。クレジットカードの支払いや奨学金の返済の遅延、分割払いで購入したスマートフォンの引き落とし不調などがある場合、ブラックリストに登録され、住宅ローン審査に通らないケースがあります。
信用情報に登録された記録は、4年~10年など一定期間が過ぎれば消えますが、滞納などの内容によって、記録が消えるまでの期間は異なります。
CIC・JBA・JICCなどの信用情報機関に登録されている信用情報は、自分自身の情報であれば情報開示請求制度を利用して確認することができます。 不安がある場合は取り寄せてみましょう。
この他、車のローンなど他の借入金額が多い場合、返済可能額が低いとみなされる可能性もあります。
なお、本審査では、借入する人の支払い能力や物件の担保価値の問題が問われますが、書類の不備や、事前審査と本審査で申告内容が異なるのは良くないとされます。



書類の不備については、再提出で問題がないこともありますが、年収などの項目で本審査の時に事前審査と金額が変わっていたなどは、非常に良くないので注意しましょう。
事前審査・仮審査に落ちた時の対処法
住宅ローン審査に落ちたからといって、購入を諦める必要はありません。対応方法を説明します。
自己資金を増やす
希望どおりの融資額を得たいけど、審査に落ちたという場合は、返済体制を作り直すのも1つの方法です。貯蓄や親からの借入などを利用して自己資金比率を高めると、ローンにとおりやすくなるだけでなく、金利が優遇されることもあります。
オートローンなど大口の借入を貯蓄から返したり、家の購入を少し延ばして貯蓄したりするのも良い選択でしょう。



また、夫婦のペアローンや収入合算という方法もあります。


他の金融機関に申し込む
審査に通らなかった場合でも、他の金融機関で融資が可能な場合もあります。ただし、借入の希望条件を見直したり、信用情報の照会をしたりしたうえで申し込みましょう。
なお、審査落ちの記録は信用情報に残っています。住宅ローンの本審査に落ちた後、別の金融機関で申し込む場合は、6カ月程度期間を空けるのが良いでしょう。
借入希望額を下げる
事前審査の段階の審査落ちの理由に、返済比率が高すぎるなどが考えられる場合は、購入する物件を見直すことも対応方法の1つです。
例えば、新築にこだわらずに中古物件であれば新築よりグレードが高い、立地が良いなどの物件をより安く購入できるかもしれません。
近年では、金利の変動を気にして、無理な借入を避けようという動きも広がっています。住宅金融支援機構の調査結果では、住宅ローン借入者のうち39.1%=約4割が、日本銀行の金融政策変更の影響で「住宅ローン選択」に変化があったと回答しました。



変化の内容としては「借入額を減らした」「変動金利タイプから固定金利タイプへ見直した」などの声が寄せられています。
住宅ローン審査に精通した仲介会社を選ぶ
仲介会社によって、金融機関ごとの審査の特徴と傾向を把握してアドバイスできるかどうかが異なります。特に事前審査・仮審査で落ちる理由に当てはまる条件をお持ちの方や、個人事業主で審査に通るか不安のある方は、経験豊富なアドバイザーのいる仲介会社を選ぶのがおすすめです。
また、住宅ローンの借入金額は借りられるだけ借りればよいというものではありません。借入金の適正額というのは人それぞれで、毎月の収入や家族構成、家族の人生設計によっても異なります。融資申請者が安心して返済できる額について、きちんとアドバイスしてくれる不動産仲介会社を選ぶのもポイントです。
スムナラでは金融機関ごとの特色を理解して、中古住宅購入希望者の条件にあった方法と金額を提案します。また、現時点では審査に通らない場合でも、時期を待てば通る可能性がある場合もあります。スムナラではそのための事前の対策をして将来住宅購入のための計画を一緒に立てて中長期的なサポートもしています。
参考:
国土交通省「令和5年度 住宅経済関連データ」
住宅金融支援機構「令和6年度 住宅ローン利用者の実態調査結果」
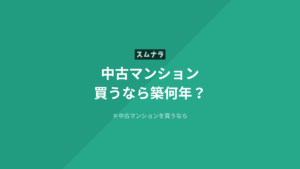
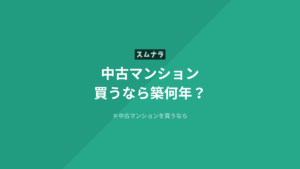
無料オンラインセミナー
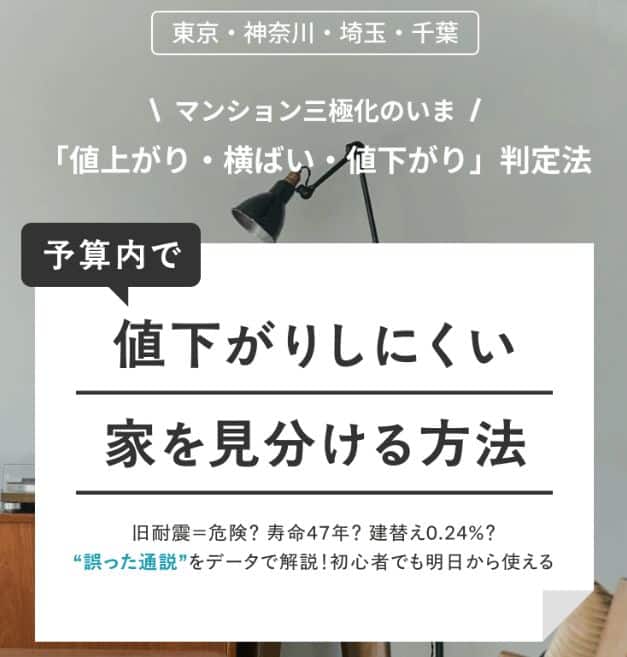
中古マンションを購入検討の方必見!
【セミナーの内容】
- 市場は「大吉・中吉・凶」の三極化
- 予算内で「中吉以上」を選ぶ方法
- 築年・立地・管理の3視点で探す
- 資産性・耐震性・寿命・建替えを解説
- 初心者歓迎・家族参加OK
- セールスなしで安心参加
新規借入と借り換えで審査基準は変わる?



借り換えの場合の事前審査の基準は、新規借入の場合と大きく変わりません。
借り換えの場合で重視されるのは、年齢と返済比率の2つです。
借り換えの場合、これまでの返済で借入総額は減っているものの、完済までの年限設定は短くなっています。返済の月額が増やせる状況であれば、返済総額はさらに減らせますが、年収などに変化があって、家計の中の返済比率が上がっている場合は、借り換えには慎重になる必要があるでしょう。
まとめ
住宅ローン事前審査・仮審査とはどのようなものか、審査基準や落ちた時の対処法などを解説しました。
住宅ローンの審査に通るには、事前の調査や自己資金・家計の見直し、無理のない返済月額と借入額の設定が有効です。不動産仲介会社の担当者の借入の知識、金融機関ごとの傾向、対策を理解しているか、中長期的な計画設計に相談に乗ってくれるかなどで結果が変わってきます。仲介会社を賢く選んで理想の住宅購入と将来の生活を実現させましょう。