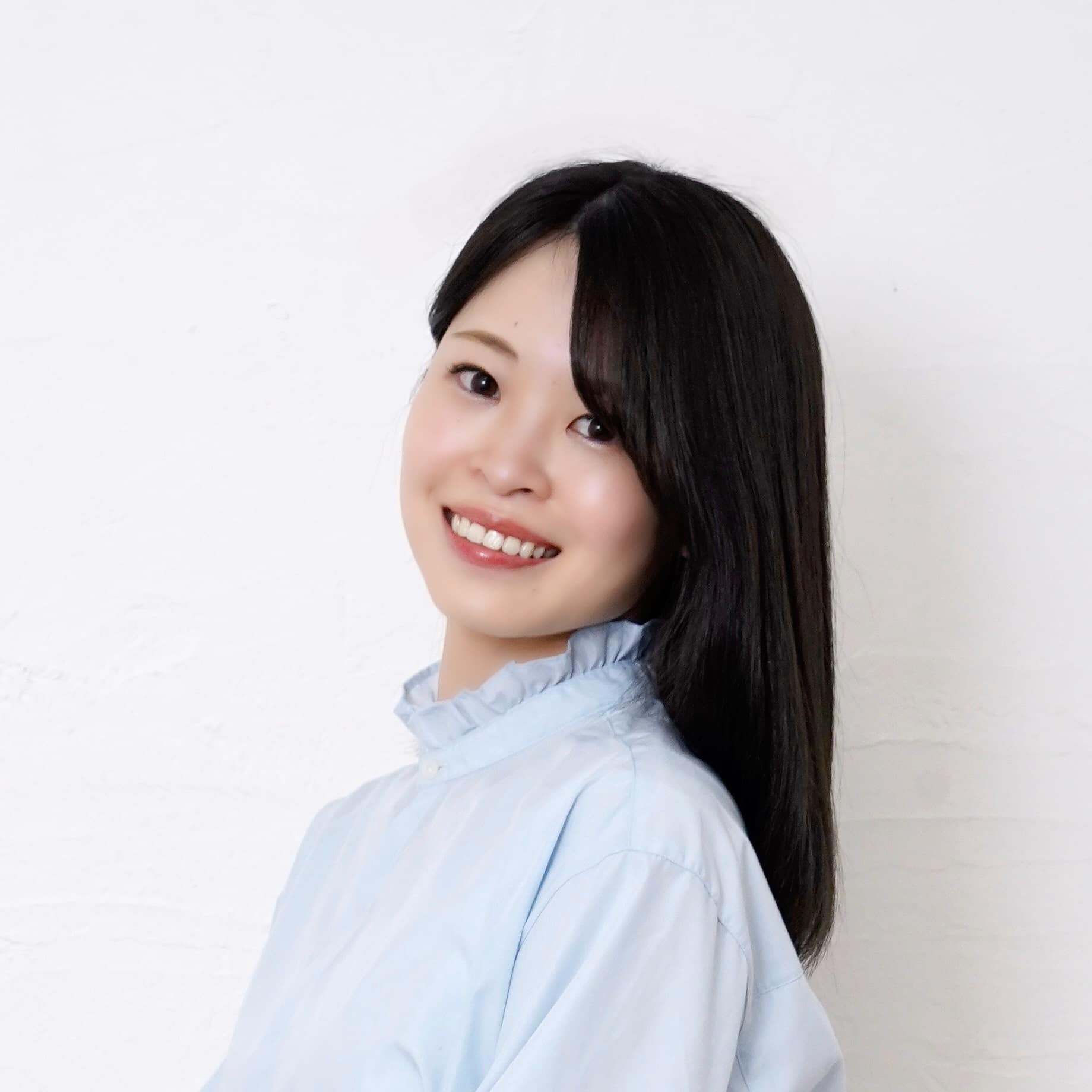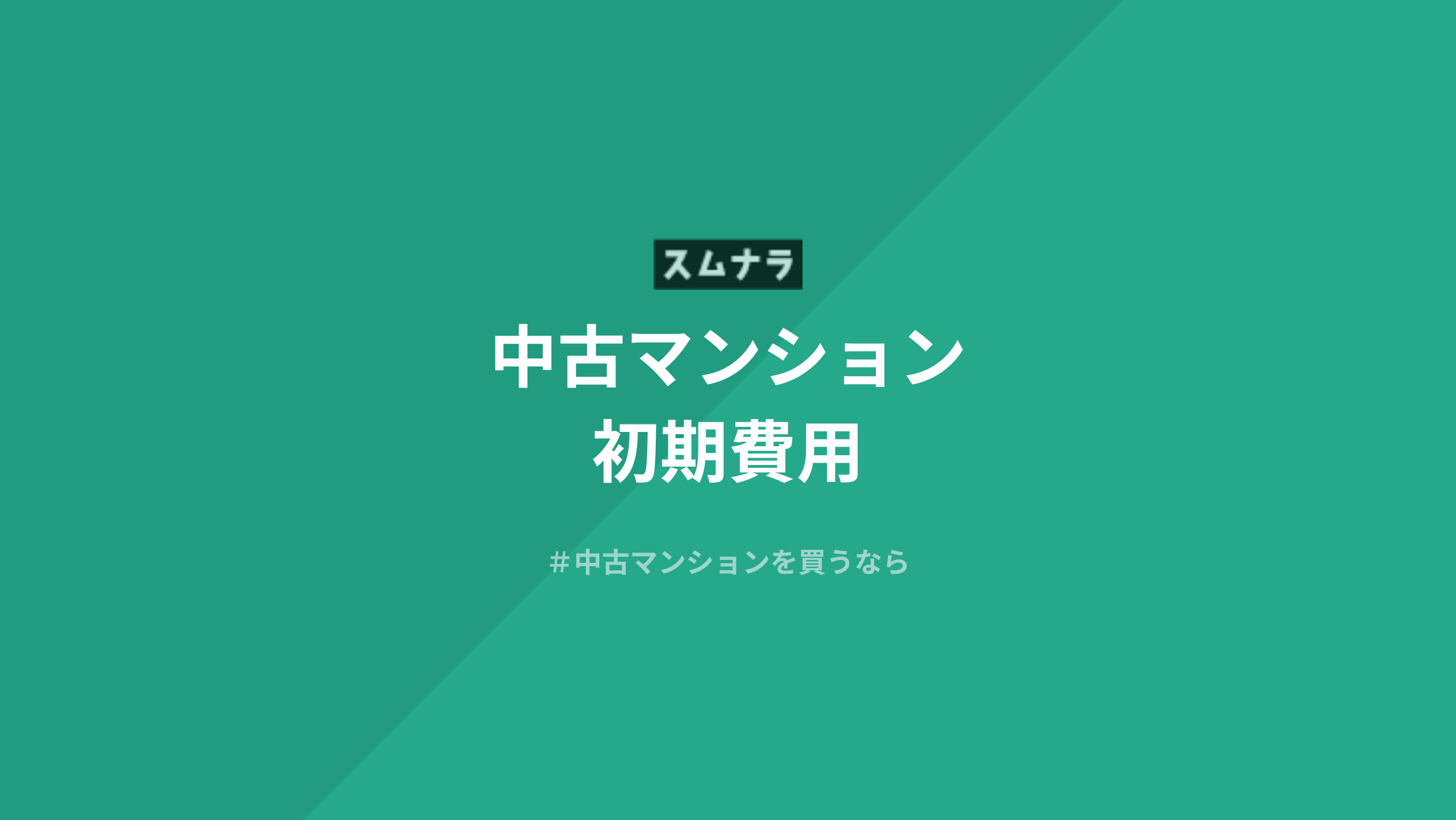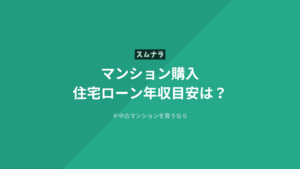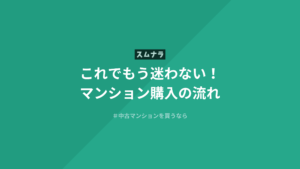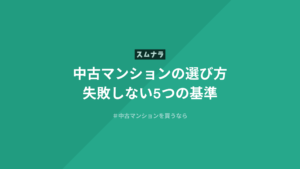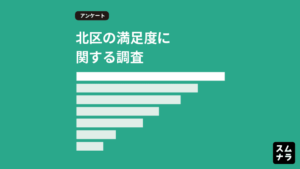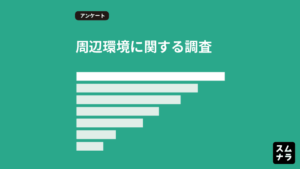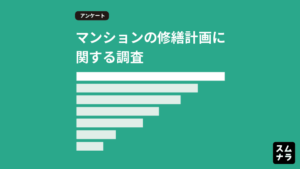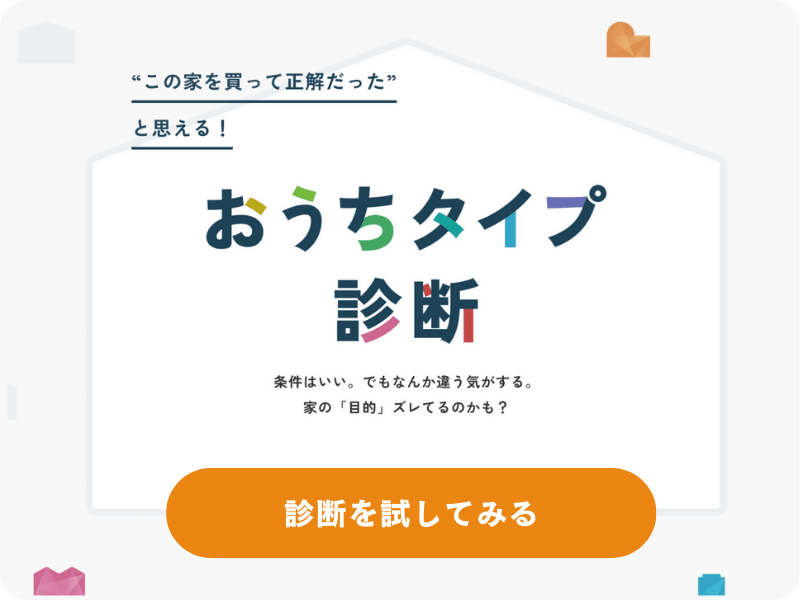中古マンションの購入を検討している時、気になるのが初期費用の金額ではないでしょうか。 賃貸か購入か迷っている場合にも、購入にかかるお金の全体像を知っておきたいという方は多いはずです。また、中古マンションの購入時にかかる初期費用や諸費用は項目が多く算出方法も複雑です。初期費用が想像以上にかかったり、あとで想定外の費用が判明したという場合も少なくありません。適切な費用を適切に見積もり削れる箇所をしっかりと見極めるには、マンション売買に精通し細かなアドバイスをくれる仲介会社を選ぶのがおすすめです。
この記事では、中古マンションの購入時にかかる費用の内訳をわかりやすく整理して説明します。マンションの金額ごとのシミュレーションや節約の方法もお伝えするので参考にしてください。
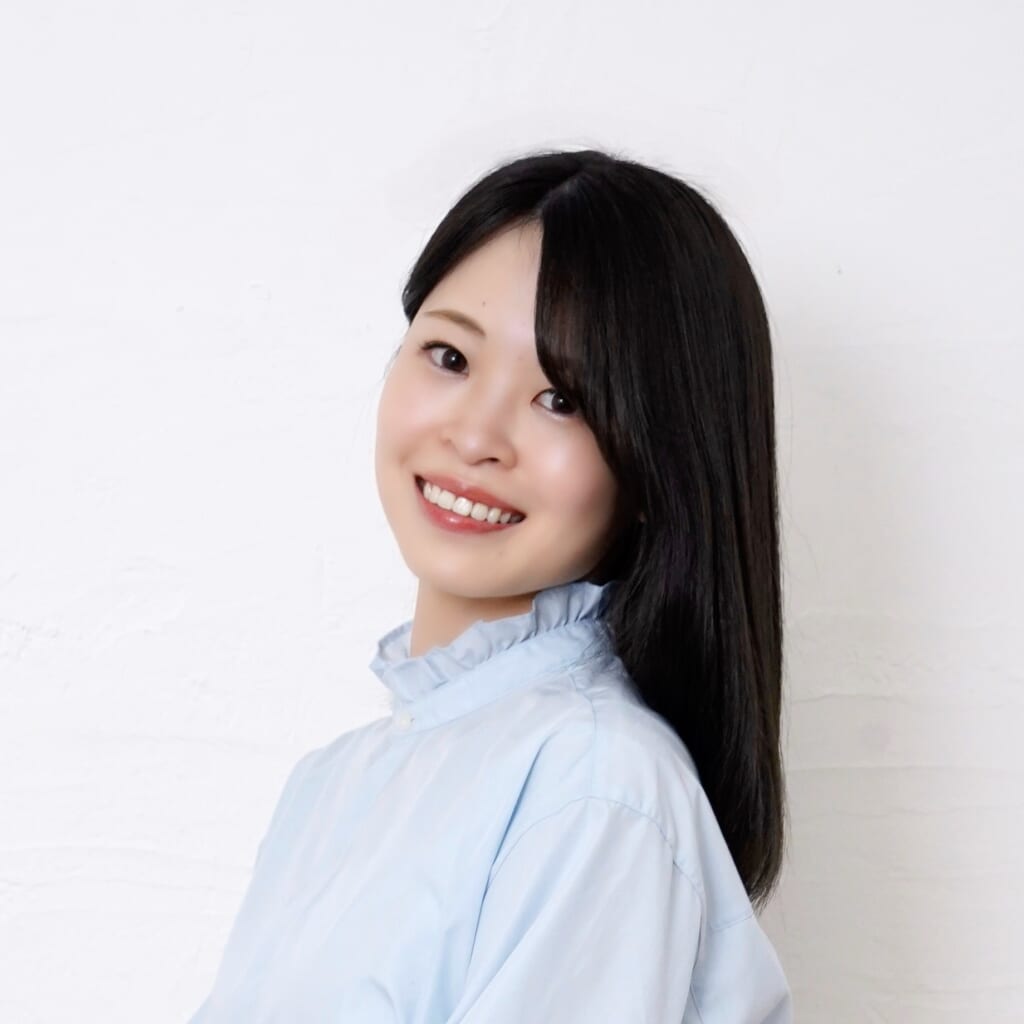
宅地建物取引士(合格)
熊本大学を卒業後、不動産デベロッパーで勤務する傍ら、ライターとして活動している。不動産贈与、相続、売買、リフォームなど幅広いジャンルの執筆を行い、特に、不動産、金融系の分野を得意とする。「ロジカルでわかりやすい文章により情報を届け、人生が良い方向に進むきっかけをつくる」ことをモットーに掲げている。
本記事の内容は2025年7月23日時点の情報に基づいており、不動産市場の状況や関連法規、税制などは将来変更される可能性があります。最新の情報については、公式の情報源をご確認ください。
中古マンション販売サイト「スムナラ」なら、
感覚ではなく数字と根拠で、後悔しない住まい選びができます。
 世田谷区
世田谷区
空間がゆるやかに繋がる専用庭付きリノベーション住宅「祖師ヶ谷大蔵センチュリーマンション」1階
5,180万円
 世田谷区
世田谷区
都会的な利便性と豊かな自然が調和するリノベ済み物件「尾山台リバーサイドハイデンス」1階
4,580万円
 千葉市
千葉市
都内へ好アクセスな都市と自然が共存する暮らし「エヴァーグリーン千葉中央」4階
2,680万円
 茅ヶ崎市
茅ヶ崎市
約90㎡のゆとりと明るいリビングが魅力の3LDK「コスモ茅ヶ崎プレシオ」9階
1,980万円
 横浜市
横浜市
緑豊かな住環境と広々とした3LDK「三保ガーデン」
3,580万円
 北区
北区
築浅で最新の設備が満載!駅チカ2LDK物件「プレシスヴィアラ田端」9階
7,870万円
中古マンションを買う時にかかる費用は?諸費用の目安

中古マンションを買う時にはマンション価格の他に、各種手数料や税金、住宅ローンの借入に必要な費用など、さまざまな諸費用がかかります。
一般的には、中古マンションの購入にかかる諸費用の目安は、マンション価格の約6%〜10%です。
この諸費用の内訳や金額は、物件の条件やローンの組み方、利用する仲介会社によっても変わってきます。
 坪川
坪川 物件によって幅がありますが「10%」と多めに計算しておくと安心です。
中古マンション購入時にかかる諸費用の内訳


中古マンションを購入する場合、物件価格とは別にさまざまな費用が必要になります。これら諸費用は「売買契約時」「引き渡し時」「入居後」の3つのタイミングで諸費用がかかります。
どの費用がいつ、どのくらいかかるのかを事前に把握しておけば、資金計画の見通しが立ちやすくなるでしょう。
初期費用
マンションの売買契約を締結する時には、初期費用が必要になります。ここでは、初期費用の内訳のうち代表的な項目について説明します。
【仲介手数料】
仲介手数料とは、マンションの売買を仲介する不動産会社に支払う費用です。売買契約の締結時に半分、引渡し時に残りの半分を支払うことが多いでしょう。仲介手数料は、国土交通省によって上限額が決められており、以下のように計算されます。
| 物件価格(税抜) | 報酬の上限額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 物件金額×3%+消費税 |
| 200万円超 ~400万円以下 | 物件金額×4%+2万円+消費税 |
| 400万円超 | 物件金額×3%+6万円+消費税 |


【印紙税(売買契約書)】
マンションの売買契約書には印紙を貼る必要があり、印紙税がかかります。印紙税はマンション価格に応じて違います。なお、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成された契約書には、以下の軽減税率が適用されています。
| 契約金額 | 軽減税率を適用した 印紙税額 |
|---|---|
| 100万円超 ~500万円以下 | 1千円 |
| 500万円超 ~1千万円以下 | 5千円 |
| 1千万円超 ~5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円超 ~1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超 ~5億円以下 | 6万円 |
参考:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」
参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
参考:公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会「不動産取引に関するお金の知識」
引き渡し時にかかる費用
契約を完了し、引き渡しを受ける際にもいくつか費用が必要になります。
【融資事務手数料】
住宅ローンを利用する場合、金融機関に対して融資事務手数料を支払います。
この融資事務手数料には、定額型と定率型の2種類があります。金額は金融機関によって差がありますが、定額型は3.3万円程度、定率型は借入額の2.2%程度が標準的です。



どちらが適用されるかは、金融機関やローンプランによって異なります。
【保証料】
住宅ローンを利用する際は、金融機関が指定する保証会社へ支払う保証料もかかることがあります。これは、住宅ローンの返済が滞った場合に、保証会社が支払いを一時的に肩代わりしてもらうための費用です。その後、保証会社は借主へ肩代わりした金額の返済を求める仕組みになっています。



保証料の金額は、借入額や返済期間によって変わりますが、借入額の2%前後が多く、借入額が大きい程高くなります。
【印紙税(住宅ローン契約書)】
住宅ローンの契約書にも売買契約書と同様に印紙が必要で、印紙税がかかります。初期費用の際に説明しましたが、売買契約書などの印紙税には軽減措置が適用されることがあります。
ただし、住宅ローン契約書はその対象に含まれていないため、以下の印紙税が必要です。
| 契約金額 | 印紙税の金額 |
|---|---|
| 100万円超 ~500万円以下 | 2千円 |
| 500万円超 ~1千万円以下 | 1千円 |
| 1千万円超 ~5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円超 ~1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超 ~5億円以下 | 10万円 |
【火災保険料】
マンションを購入する際には、火災保険への加入が必要です。法律上の義務ではありませんが、多くの金融機関では、住宅ローンの融資の条件として加入が求められます。金額は契約期間や補償内容次第で変動します。
選ぶプランによって補償範囲や自己負担額が異なるため、「とりあえず安いものを選ぶ」のではなく、物件や家族構成に応じた補償内容を選択しましょう。


【登録免許税】
不動産を取得した際には、その権利を法的に登録する手続きである「登記」を行います。 手続きには、登録免許税とよばれる税金をおさめる必要があります。これは不動産登記にかかる税金です。
なお、中古マンションを購入して住宅ローンを利用する場合、一般的に 土地の所有権移転登記 及び 建物の所有権移転登記 、またローンの担保としての抵当権設定登記が必要になります。
それぞれ、登記の際には以下の登録免許税が必要となりますが、期限付きで軽減措置があります。
- 土地の所有権移転登記:不動産価額の1.5%(令和8年3月31日まで軽減)
- 建物の所有権移転登記:不動産価額の1.5%0.3%(令和9年3月31日まで軽減)
- 抵当権設定登記:借入額の0.1%(令和9年3月31日まで軽減)
【司法書士への報酬】
所有権移転登記や抵当権設定登記は、専門的な知識が求められるため、通常司法書士に依頼します。司法書士への報酬は、数万円~5万円程度が目安です。
参考:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
参考:公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会「不動産取引に関するお金の知識」
入居後にかかる費用
マンションを購入したあとも、税金など、さまざまな費用が必要になります。
【不動産取得税】
不動産取得税は、不動産取得に対して、一度だけ課される地方税です。登録免許税と同じく令和9年3月31日まで軽減税率が適用されています。税率は不動産価額の3%です。



ただし、さらに、築年数や床面積に応じた控除制度もあり、実際の納税額が軽くなるケースもあります。
【固定資産税・都市計画税】
毎年1月1日時点の土地や建物などの所有者には、固定資産税が課されます。
また、物件が市街化区域内にある場合は、都市計画税もあわせて課税されます。都市計画税が課税されるかどうかは、物件の所在地や区域区分によって異なります。税率は以下のとおりです。
- 固定資産税:課税評価額の1.4%が標準
- 都市計画税:課税評価額の0.3%以下(市区町村によって異なる)
新築や一定の条件を満たす中古住宅には、軽減措置が適用されます。



マンションの売買時は日割り計算をして、引き渡し日以降の分を買主が負担するのが一般的です。
【管理費・修繕積立金】
マンションに住みはじめると、毎月の「管理費」と「修繕積立金」が必要になります。管理費はマンション共用部の維持・管理のために徴収される費用で、平均で月額1万円~2万円程度です。
修繕積立金は将来の大規模修繕に備える費用で、月額1.5万円弱が目安です。


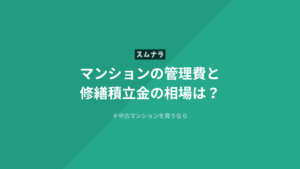
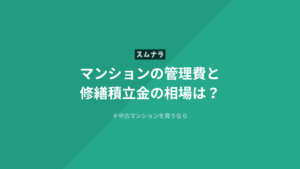





いずれも物件によって金額が異なります。
【引っ越し費用】
マンションを購入して住む場合は、引っ越し費用も必要です。費用は荷物の量や移動距離、時期などで変動しますが数万円から十数万円が目安です。
参考:総務省「不動産取得税」
参考:総務省「固定資産税」
参考:総務省「都市計画税」
参考:国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」
【物件金額別】諸費用のシミュレーション


マンションの物件金額が2,000万円、3,000万円、4,000万円、5,000万円の場合の各諸費用をシミュレーションしましたので、参考にしてください。
なお登録免許税や不動産取得税、固定資産税・都市計画税に関わる不動産価額は、物件金額と同等(土地が約1/3、物件が約2/3)に算出し、住宅ローンは物件金額の80%の借り入れを想定しています。
2,000万円の中古マンションを購入した場合
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 約72万円(上限額) |
| 印紙税 (売買契約書) | 1万円 |
| 融資事務手数料 | 約3万円(定額型) |
| 保証料 | 約32万円 (借入額の2%想定) |
| 印紙税 (住宅ローン契約書) | 2万円 |
| 火災保険料 | 約10万円(10年) |
| 登録免許税 | 約16万円(土地の所有権移転:価額の1.5%、建物の所有権移転:価額の0.3%、抵当権設定:借入額の0.1%) |
| 司法書士への報酬 | 約5万円 |
| 不動産取得税 | 0円(控除を想定) |
| 固定資産税・都市計画税 | 約13万円(軽減措置適用、半年分想定) |
| 管理費・修繕積立金 | 約3万円 |
| 引っ越し費用 | 約10万円 |
| 合計 | 約163万円 |
3,000万円の中古マンションを購入した場合
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 約105万円(上限額) |
| 印紙税 (売買契約書) | 1万円 |
| 融資事務手数料 | 約3万円(定額型) |
| 保証料 | 約48万円 (借入額の2%想定) |
| 印紙税 (住宅ローン契約書) | 2万円 |
| 火災保険料 | 約12万円(10年) |
| 登録免許税 | 約23万円(土地の所有権移転:価額の1.5%、建物の所有権移転:価額の0.3%、抵当権設定:借入額の0.1%) |
| 司法書士への報酬 | 約5万円 |
| 不動産取得税 | 0円(控除を想定) |
| 固定資産税・都市計画税 | 約19万円(軽減措置適用、半年分想定) |
| 管理費・修繕積立金 | 約3万円 |
| 引っ越し費用 | 約10万円 |
| 合計 | 約231万円 |
4,000万円の中古マンションを購入した場合
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 約138万円(上限) |
| 印紙税 (売買契約書) | 1万円 |
| 融資事務手数料 | 約3万円(定額型) |
| 保証料 | 約64万円 (借入額の2%想定) |
| 印紙税 (住宅ローン契約書) | 2万円 |
| 火災保険料 | 約15万円(10年) |
| 登録免許税 | 約31万円(土地の所有権移転:価額の1.5%、建物の所有権移転:価額の0.3%、抵当権設定:借入額の0.1%) |
| 司法書士への報酬 | 約5万円 |
| 不動産取得税 | 0円(控除を想定) |
| 固定資産税・都市計画税 | 約25万円(軽減措置適用、半年分想定) |
| 管理費・修繕積立金 | 約3.5万円 |
| 引っ越し費用 | 約10万円 |
| 合計 | 約297万円 |
5,000万円の中古マンションを購入した場合
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 約171万円(上限額) |
| 印紙税 (売買契約書) | 1万円 |
| 融資事務手数料 | 約3万円(定額型) |
| 保証料 | 約80万円 (借入額の2%想定) |
| 印紙税 (住宅ローン契約書) | 2万円 |
| 火災保険料 | 約18万円(10年) |
| 登録免許税 | 約39万円(土地の所有権移転:価額の1.5%、建物の所有権移転:価額の0.3%、抵当権設定:借入額の0.1%) |
| 司法書士への報酬 | 約5万円 |
| 不動産取得税 | 0円(控除を想定) |
| 固定資産税・都市計画税 | 約31万円(軽減措置適用、半年分想定) |
| 管理費・修繕積立金 | 約4万円 |
| 引っ越し費用 | 約10万円 |
| 合計 | 約364万円 |
中古マンション購入時の諸費用を節約する方法


中古マンション購入時には、物件価格以外にも多額の費用がかかります。できれば、少しでも予算を抑えるために、見直しや工夫のポイントを知っておきましょう。
ここでは、実際に節約に繋がりやすい方法を3つ紹介します。
仲介手数料の値下げを交渉する
仲介手数料は、前述のとおり法律で定められた上限額があります。これは、あくまで「上限」で、必ずしもその金額を支払わなければならない訳ではありません。
つまり、交渉次第で値下げしてもらえる可能性は残されています。例えば長年買い手がつかず、売れ残っていた物件の場合、売主も仲介会社も早く契約を決めたいと考えている可能性があります。



このような背景があるなら「この物件が気に入っているが予算に限りがある」と伝えれば、相談しやすいでしょう。
保証料のかからない住宅ローンを利用する
住宅ローンのなかには、保証料がかからないタイプを用意している金融機関も存在します。その場合、保証料の代わりに定額の事務手数料が発生しますが、総費用では安くなるケースもあります。
ただし、逆に、事務手数料型の方が高くなることもあるため要注意です。



複数の金融機関の条件を比較して、最終的に支出がどれくらいになるのかをシミュレーションして選びましょう。
火災保険の補償範囲を見直す
火災保険は、住宅ローンの融資条件として加入しなければならないことが多いですが、補償内容の見直しで、保険料を抑えられる場合があります。
例えば、水災や地震などのオプションを見直すと大幅に節約できることもあります。ただし補償を外すには、必要な補償と不要な補償を慎重に精査する必要があります。



自治体が発行しているハザードマップなどを活用し将来的なリスクを見極め、負担が大きくなるおそれがある場合には、保証が必要です。
まとめ
中古マンションの購入時にかかる初期費用や諸費用の内訳とマンションの金額ごとのシミュレーション、節約のヒントについて解説しました。
中古マンションの購入時には、物件価格だけでなく、まとまった金額の初期費用や諸費用が必要になります。購入後に想定外の出費が必要となって、困らないよう、購入前に正しく理解しておきたいところです。また初期費用や諸費用を上手に抑えられれば、その分をリフォームやインテリアの購入費などに回す選択肢も生まれます。
スムナラは中古マンションの購入に関する知識が豊富です。初期費用や諸費用、節約できるポイントを細やかにご説明するのはもちろん、節約に繋がるポイントについても丁寧にサポートします安心して、そしてお得に。かつ納得して中古マンションを購入したい方は、ぜひスムナラにご相談ください。