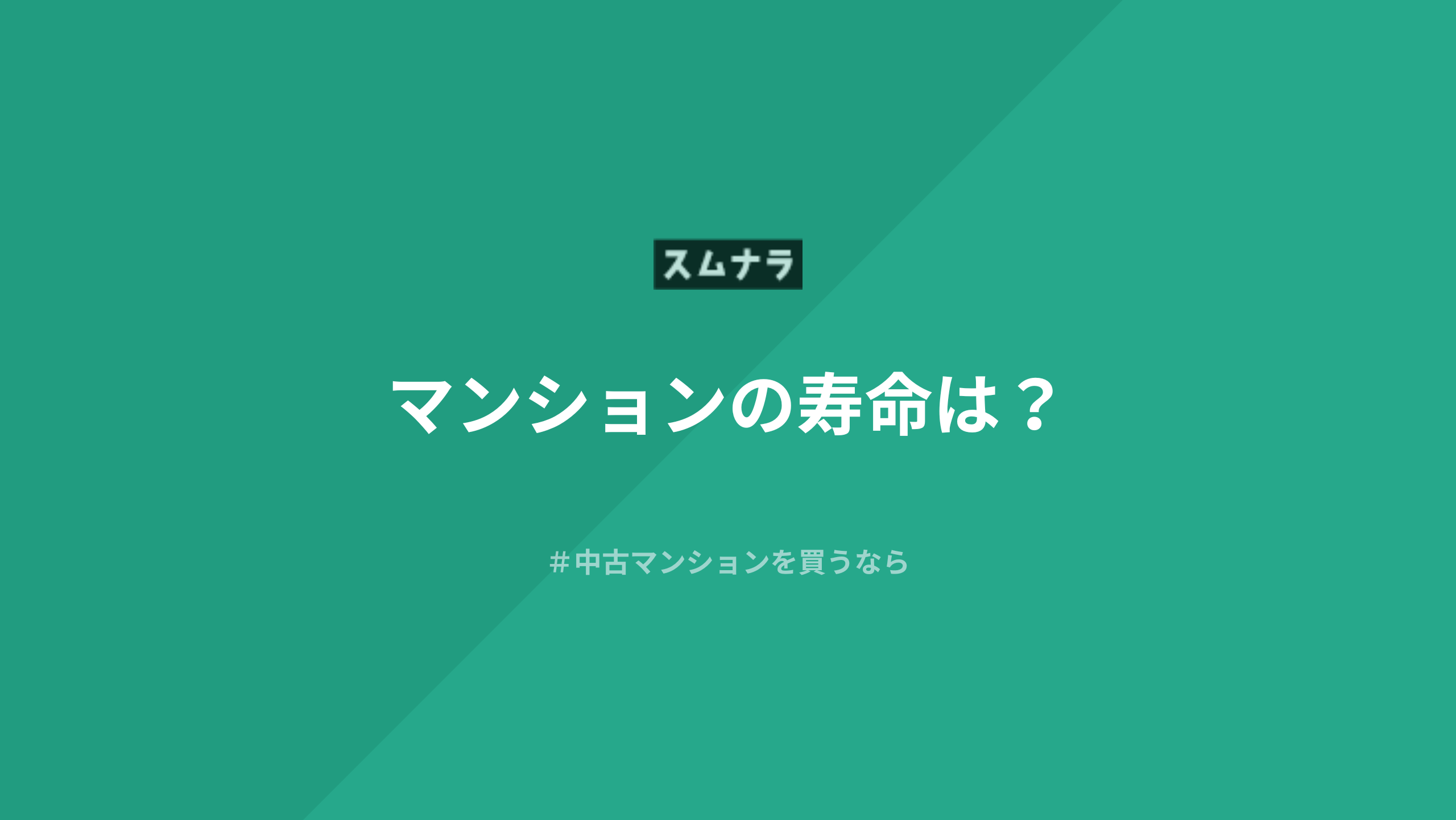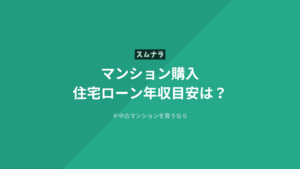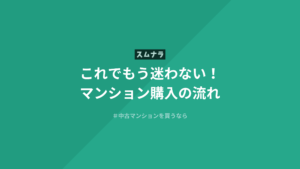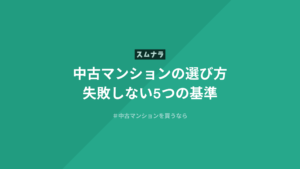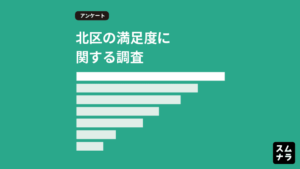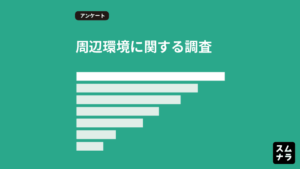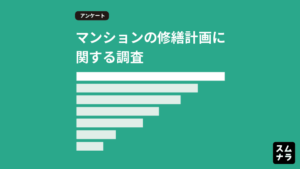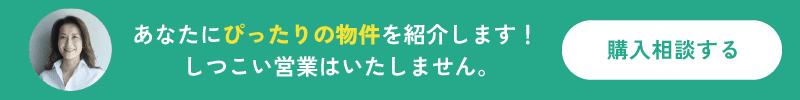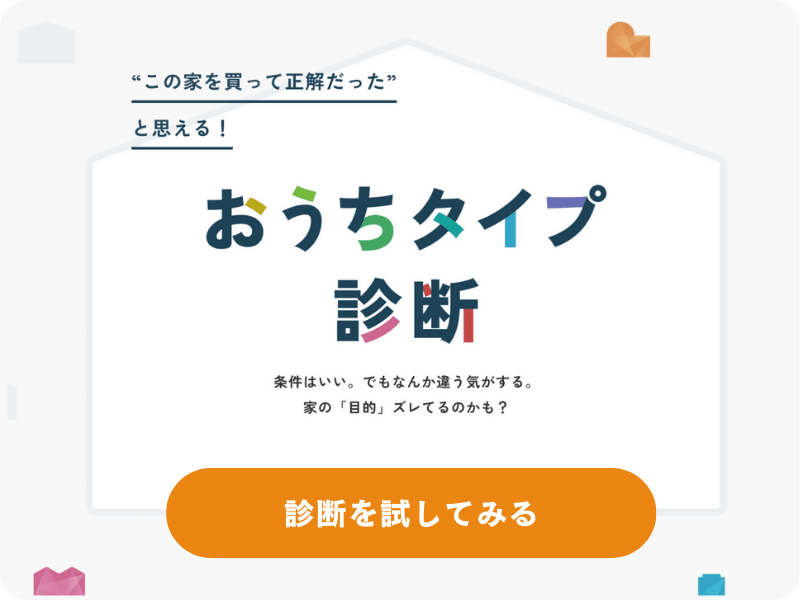みなさんがお住まいのマンションは、どのくらい寿命があるのでしょうか。いつまで安心して住んでいられるのか、高い修理費用が必要になった時どうすればいいのか、気になりますね。
マンションの修繕を計画的に行っていれば、「経年劣化のため建て替えが必要になって、一時的に退去しなければならない」というような事態は避けられます。
本記事ではマンションの寿命とはどんなものか、耐用年数と寿命との違い、寿命の考え方や延命方法などを解説します。マンションに長く愛着を持って暮らすための参考にしてください。

宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
元不動産営業のWEBライター。不動産会社で店長や営業部長として12年間勤務し、売買仲介・賃貸仲介・新築戸建販売・賃貸管理・売却査定等、あらゆる業務に精通。その後、不動産Webライターとして大手メディアや不動産会社のオウンドメディアで、住まいや不動産投資に関する記事を多く提供している。不動産業界経験者にしかわからないことを発信することで「実情がわかりにくい不動産業界をもっと身近に感じてもらいたい」をモットーに執筆活動を展開中。
本記事の内容は2025年1月16日時点の情報に基づいており、不動産市場の状況や関連法規、税制などは将来変更される可能性があります。最新の情報については、公式の情報源をご確認ください。
無料オンラインセミナー
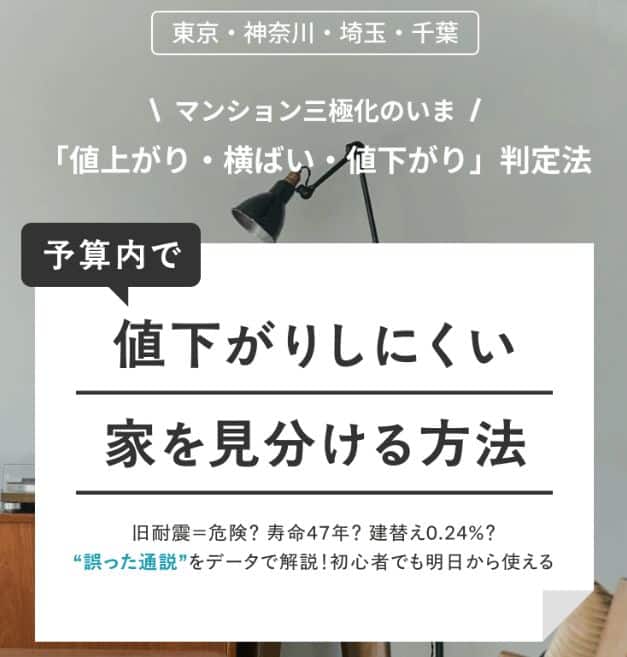
中古マンションを購入検討の方必見!
【セミナーの内容】
- 市場は「大吉・中吉・凶」の三極化
- 予算内で「中吉以上」を選ぶ方法
- 築年・立地・管理の3視点で探す
- 資産性・耐震性・寿命・建替えを解説
- 初心者歓迎・家族参加OK
- セールスなしで安心参加
マンションの寿命はどれくらい?
マンションの寿命は、どのくらいの期間となるのでしょうか。この項では寿命が何を指し、何年くらいに相当するのかを解説します。
寿命=耐用年数ではない
マンションの寿命を「老朽化などによって住むための快適性や安全性が損なわれた状態」と考えた場合、本当の意味で寿命を迎えたマンションは、現状ではほとんどありません。
マンションは明らかな寿命を迎える前に、経済的理由、オーナーチェンジ、耐震性のリスク回避、災害など、さまざまな理由で建て替えが行われることはありますが、2004年~2024年4月までの時点で297棟と、ごく少数で、実際は修繕と管理によって現存している物件が多いといえます。
一方で税務や金融の世界では、マンションにかかる税金や減価償却費の計算などに使われる税務上の資産価値を表す法定耐用年数という基準があります。
法定耐用年数を過ぎたマンションだとしても寿命を迎えた訳ではないので、住み続けることができます。
 滋野
滋野ただし、法定耐用年数を過ぎたマンションは、経費として減価償却できなくなったり、中古で売買する際に銀行の融資基準が厳しくなったりするかもしれません。
マンションの平均寿命は約68年、寿命は最長100年以上
国土交通省が平成25年に公表した調査結果によると、マンションの平均寿命は68年でした。また、最長の寿命は、新耐震基準の建物で、適切なメンテナンスが行われている場合100年以上と想定されています。公的な住宅性能評価書に記載される最高等級3の場合には、最長の寿命は90年とされます。
参考:国土交通省「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について」
マンションの耐用年数は47年
マンションの耐用年数と表現される場合、通常「法定耐用年数」のことを指しています。法定耐用年数は税務上の資産価値が残っている年数です。
法定耐用年数は建物の構造や用途(住宅・事務所・飲食店)によって違い、マンションの場合鉄筋コンクリート造で、47年が耐用年数とされます。
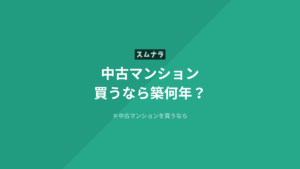
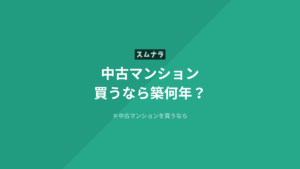
マンションの寿命は何で決まる?
マンションの寿命は、用途によって使用する基準が違い、主に以下の3種類の耐用年数が使われています。それぞれについて詳しく解説します。
- 法定耐用年数
- 経済的耐用年数
- 物理的耐用年数
法定耐用年数
法定耐用年数は税務や金融で使用される指標で、税務上の資産価値が残っている年数ですが、減価償却費の計算や、中古マンションの融資の基準として使われています。仮に鉄筋コンクリート造で築10年のマンションの場合、建物価格2,000万円であれば、減価償却費は以下のように計算します。
償却率は建物の耐用年数によって決まっているため、法定耐用年数までの年数をまずは計算する。
法定耐用年数までの年数=構造ごとのマンションの耐用年数 -(築年数 ×0.8)47年‐(10年×0.8)=39年。
39年目の定額法償却率は0.026。
2,000万×0.026=520,000円(減価償却費)
この52万円が、確定申告などの際に、この年の経費として認められます。
マンションの構造ごとの、法定耐用年数は以下のとおりです。鉄骨よりも鉄筋コンクリート(RC)の方が耐用年数が長くなります。
| 構造(住宅用の建物) | 耐用年数 |
|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 47年 |
| れんが造・石造・ブロック造 | 38年 |
| 鉄骨造(4mmを超えるもの) | 34年 |
経済的耐用年数
建物の経済的価値に注目し、経済価値がなくなるまでの年数を算出するのが経済的耐用年数です。
経済的耐用年数は建物の経過年数や劣化度合いの他に、立地に左右される基準です。人気のある場所にあるマンションは古くても住む価値があるとされ、経済的耐用年数が長くなります。



逆に都市部の一等地では、まだ使える建物でも「建て替えた方が、より多くのお金を生む」という理由で経済的耐用年数が短くなることもあります。
物理的耐用年数
物理的耐用年数は、建物自体が使用可能かどうかの指標で、いわゆる建物の物理的寿命の意味で使われます。
マンションの物理的な寿命は建築技術の進歩で年々伸びています。「建物の耐久性を評価するための基準」である「劣化対策等級」では、住宅が限界状態に至るまでの期間によって、以下のように等級がわかれています。



寿命は、等級3の場合、住宅が限界状態に至るまでの期間は最大90年です。
- 等級3…住宅が限界状態に至るまでの期間が概ね3世代(75~90年)
- 等級2…住宅が限界状態に至るまでの期間が概ね2世代(50~60年)
- 等級1…建築基準法に定められた対策がなされている(最低基準)
また、長期優良住宅に認定されれば、物理的な耐用年数は最長100年という基準が使われます。
無料オンラインセミナー
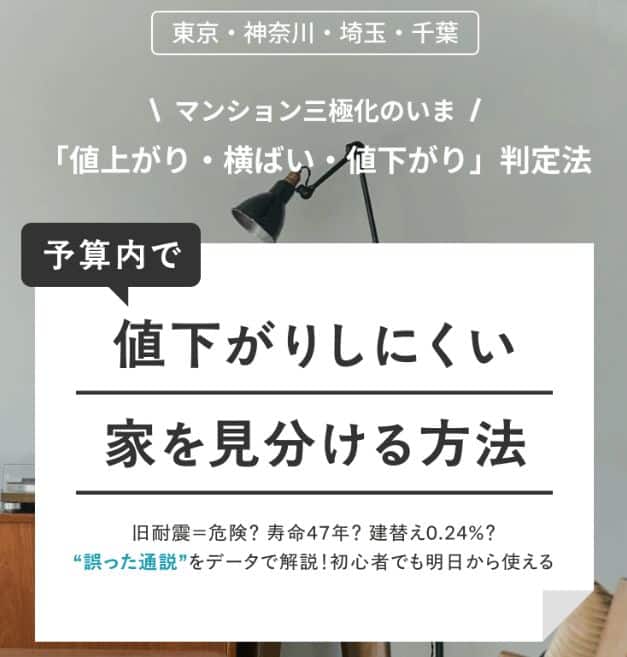
中古マンションを購入検討の方必見!
【セミナーの内容】
- 市場は「大吉・中吉・凶」の三極化
- 予算内で「中吉以上」を選ぶ方法
- 築年・立地・管理の3視点で探す
- 資産性・耐震性・寿命・建替えを解説
- 初心者歓迎・家族参加OK
- セールスなしで安心参加
寿命が近いマンションの対策
マンションの寿命の基準となる3つの指標について説明しました。マンションの耐用年数までの期間は、時間が経つに従い短くなります。タイミングによっては「そろそろ売却しようか、住み続けようか」と、迷うこともあるでしょう。寿命の近いマンションへの対応として、選択できる方法を解説します。
売却
資産価値が高いうちに手放して住み替えたい場合は、売却がおすすめです。マンションの相場価格を事前に把握したうえで、複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。
その際には、専有部分の傷みや設備の状態を良く把握したうえで、買主に確実に伝えておけば、トラブルを防げます。
比較的短い期間でマンションを手放そうとする場合、所有期間が5年、10年を過ぎるタイミングで譲渡所得税が安くなります。



タイミングによっては、節税になりますので意識しておきましょう。
建て替え
老朽化が進んだマンションは、管理組合で決議の上、建て替えというケースもあります。
建て替えの決議は区分所有者の5分の4の賛成が必要ですが、政府によって老朽マンションの建て替え促進のため、これを4分の3以下にする区分所有法改正が検討されています。現在は法案の成立時期は未定ですが、成り行きを慎重に見守る必要があります。(2025年1月時点)
マンションの建て替えには多額の費用がかかります。多くの人の関わるマンションの場合、建て替えに向けて意見をまとめるのは、とても難しいものです。



資金面の不安を低減する方法として、建て替え時に可能な限り戸数を増やし、その売買によって建て替え資金を補充する方法も使われます。
解体して土地を売却
マンションを解体して土地を売却する方法もあります。この場合、不動産ディベロッパーに土地とマンションを売却し、区分所有者の移転費用を捻出します。
ただし建物の解体費用は、鉄筋コンクリート造の場合坪単価で幅はありますが7~8万円程かかります。



区分所有者の手に残る売却益は多くはないでしょう。
メンテナンスして住み続ける
長年住み続けた家から離れたくないという年配の方が多いマンションなどでは、あらためて管理体制を強化してメンテナンスをしっかり行い、住み続けるケースもあります。



立地が良く新しい入居者が増えるような状況であれば、管理もうまく回りますが、空き家が目立つようになった場合は、住み続けるかどうかについて再検討が必要でしょう。
そのまま放置されるケースも
管理されていないマンションは空室が増え、共有部分が汚れたり劣化したりとスラム化が進む場合があります。建物の劣化がひどくなると、建材片が落下して周辺を通行する人にとっても危険です。ライフラインや排水の配管も、古い建物はメンテナンスが難しく、トラブルが起きやすいでしょう。
このような状況では、安全で快適な暮らしは難しくなります。



ここまで述べたいずれかの方法で、早めに手を打つようにおすすめします。
マンションの寿命を伸ばす方法
できれば、住み慣れたマンションに住み続けたい人は多いものです。マンションの寿命を伸ばす方法はないのでしょうか?
マンションを快適に使い続けるためには、老朽化する前から適切な維持管理をすることが必要です。
定期的なメンテナンス
新築当初から、壁面の傷みの補修やベランダ、屋根部分の防水のメンテナンスを継続していれば、建物内部の雨水・湿気の侵入や風化を防ぎ、建物の寿命を延長できます。



ライフラインや排水の点検は、漏水などのトラブルの防止に繋がるでしょう。
大規模修繕
定期的なメンテナンス以外に、10~15年ごとに外壁の塗装や本格補修、設備交換などの大規模修繕を行う必要もあります。しっかり老朽化を防げる手入れをするにはある程度の出費が必要です。建築当初から毎月修繕費用の積立を実施するか一時徴収を実施し費用をまかなう必要があります。
どこかのタイミングで耐震改修も計画に追加しておけば、暮らしの安心だけでなく資産価値の保全にも繋がります。



専有部分(居室)の設備交換、リフォームも定期的に行って、快適な暮らしを保ちましょう。
リノベーションによる蘇生
リノベーションとは、既存の建物に改修を加えて、価値や性能を高めることです。マンションの寿命は、法定年数や修繕対応だけで決まるものではありません。立地の良い場所に、長く愛着の持てるお部屋を持つ人が増えれば、建物は息を吹き返すでしょう。
マンションには、構造上リノベーションの自由度が高く、家族のニーズの個性やライフスタイルの変化に合わせた住まいづくりがしやすいという大きなメリットがあります。



長く住む中で、子ども部屋の構成を変更したり、バリアフリーに対応したりするなど、柔軟な住まいの活用を検討するのも良いのではないでしょうか。
まとめ
マンションの寿命の考え方、耐用年数と寿命との違い、寿命の対処法や延命方法などを解説しました。マンションの寿命に対応するには、普段から長期的な資金計画をして備えるとともに、管理状況を確認しておくことがとても大切です。そのうえで「こうしよう」と方針を決めておけば、安心して暮らすことができますね。ぜひ今後の参考にしてください。